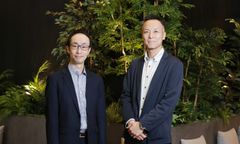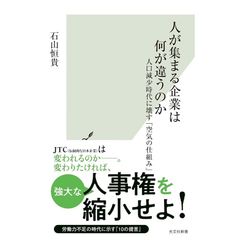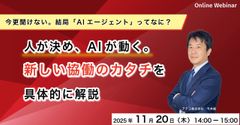さまざまな「環境変化」に法律や制度はどう対応していくのか
ProFuture株式会社 代表取締役社長/HR総研 所長 寺澤 康介

次に、企業の「働き方改革」の推進ぶりを見ると、有給休暇の消化促進や多様な勤務時間の導入などに取り組む企業が多いと言えます。それに対して、「ジョブ型雇用」については、導入の必要性を認識している企業は5割強。企業規模別の導入状況も、1001名以上の企業で4割強と、企業規模が小さくなるほど導入する割合が減っています。
さらには、ChatGPTなどの大規模言語モデルが労働市場に大きな影響を与えていると指摘されています。他にも、人的資本経営への取り組みとしては、情報開示を含めさまざまな動きが出ています。しかも、大手企業だけでなく、中堅・中小企業も重視していることがわかります。
このような環境変化を、労働法などの法律、および人事管理や制度設計の観点からどう捉えられるのか、法律や制度はこの変化にどう対応しているのか、追いついているのか、また法律や制度はどのようになっていくのか。専門家である諏訪先生、今野先生にお話を伺いたいと思います。
この先は、会員の方だけがご覧いただけます。会員の方はログインを、会員でない方は無料会員登録をお願いします。