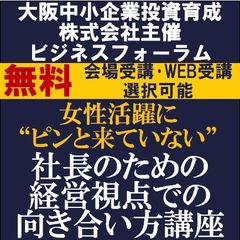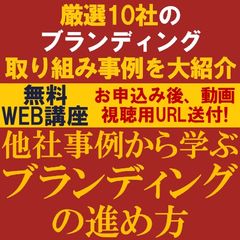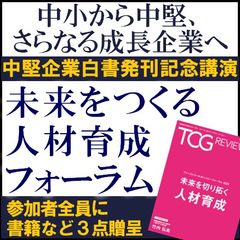賃金を決める3要素
そもそも賃金は何によって決まるか。それは、需要と供給、社内公平性、社外公平性の3つである。1.需要と供給
まず賃金は、労働市場の需要と供給によって決まる。そして需給の状況は、景気と職種によって変わる。たとえば国連のILO(国際労働機関)のレポート(Global Wage Report 2020-21)*によれば、2020年の世界の実質GDP(国内総生産)は、コロナ禍によって2009年のリーマンショック以来のマイナス成長となったが、それに伴い、世界の3分の2の国で賃金は減額または上昇抑制となった。
しかしそれ以前、たとえば経済成長いちじるしい中国では、2008年から2019年までの10年程で実質賃金が2倍以上に増えた。中国ほどではないにせよ、ほとんどの先進国では、経済成長に伴い賃金は上昇してきた。
そんな中、「失われた30年」を過ごしてきた日本だけは、賃金が30年間ほとんど変わらない。
近年ではIT業界の成長などにあわせ、技術者を中心に初任給を2千万円にするとか、優秀人材の年俸を3千万円にするといった企業が日本でも登場している。とはいえコロナ禍にある日本では、ほとんどの職種で賃金が下がるか伸びない。一部の職種だけで急激な賃金上昇が起きつつあるのだ。
2.社内公平性
だが、こんなことは20世紀(正確には第二次世界大戦後)には考えられなかった。なぜなら、戦後の日本の賃金は、社内公平性つまり「同じ会社の同期社員なら、職種が何であれ賃金は同じ」という原則を海外と比較しても特に重んじてきたからだ。
戦後の日本企業の特徴は、「日本的経営の三種の神器」という言葉に象徴される。
つまり終身雇用、年功序列、企業内労働組合である。
この三つは、日本企業を「閉じた組織」として成長させた。だから社員にとっての関心事は同期との賃金比較であり、それが公平だと感じられていれば他社より賃金が低くてもそれを甘受する人がほとんどだった。
3.社外公平性
しかし20世紀の終わりごろから、日本でもM&Aやリストラクチャリングが一般的になることで、終身雇用は実質的に終わりを告げた。人材は流動化し、賃金の他社比較が重要性を増すことになった。他社より賃金が低い会社からは、優秀人材が辞める可能性が高まったからだ。
そして21世紀は、イノベーションが企業の競争力と収益力を決める時代となった。すると、今まで「閉じた世界」だった企業で働いていた人々も、他社や社外の人材と協働せざるを得なくなる。グローバル競争の中で、社内人材だけで世界最先端のイノベーションができる会社など、もはや無いといってもよい。
しかしそうなると、今まで社内公平性だけを気にしていた社員は、社外公平性も気にするようになる。一緒に働く社外の人材が自分よりずっと賃金が高ければ、モチベーションにも影響するし、悪くすると辞めてしまう恐れがある。
とはいえこれまで日本人は、就職というより「就社」意識が強く、その会社に雇用されるということは、その会社の一員になるのだという、いわゆるメンバーシップ型の雇用意識が強かった。
だから、たとえ社外公平性に問題があっても簡単には離職しなかったのだが、ここにきて、雇用のスタイルがいわゆるジョブ型になると、社員は自律的なキャリアを形成する反面、会社に対する帰属意識は弱くなる。
だから今後は、日本でも職種別に社外公平性が強く問われ、需給がひっ迫する職種では特に賃金の上昇が目立つことになる。
日本の賃金のゆくえ
職種別に需給で賃金が決まり、また変動するということは、ジョブ型の海外では以前から当然のことであり、そういう意味では、冒頭の米国アマゾンのニュースも、それほど驚くにはあたらない。けれど問題は日本である。
日本はいまだに「フェアな賃金とは何か」という哲学において、社内公平性と社外公平性の間でどっちつかずとなっており、需給をダイナミックに反映させきることが難しい。
それに、世界でも珍しい「職種をまたがる人事異動(ローテーション)」を行っている限り、職種によって賃金を大きく変えることは、まず無理かもしれない。
アマゾンのニュースは海外では普通の話の一つに過ぎない。しかし日本企業にとっては、労働の価値観に対する一つの挑戦となっている。
(執筆者:舞田 竜宣)
※本記事は『GLOBIS 知見録』に掲載された記事の転載です。
- 1