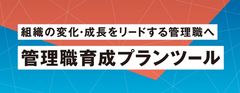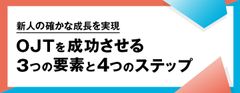「コーチング」とは
「コーチング」とは、コーチと指導を受ける相手が対話していく中で、相手が目標を実現していくために、自ら率先して行動できるよう支援・伴走するプロセスを意味する。コーチが一方的に指示を出すことはしない。あくまでも主導権は相手が握っており、コーチは相手が目標を達成できるよう、問いかけたり気づきを与えたりしてサポートしていくことが求められる。【コーチングでお悩みの方へ】コーチングスキルを向上させるためのセミナー一覧はこちら >>
【この記事も読まれています】IBM流「マネージャー起点」の人材育成・活躍支援――キーワードは「自律」と「デジタル」
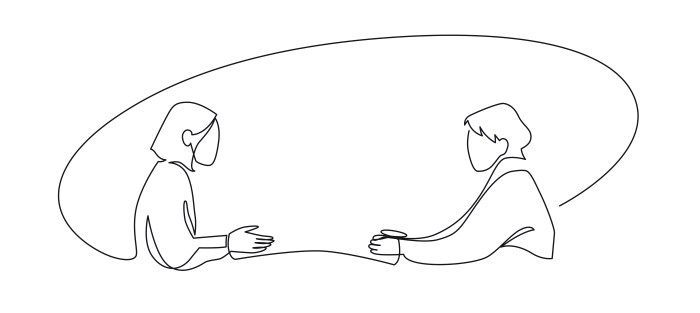
「コーチング」と関連用語の違い
「コーチング」にはさまざまな関連用語がある。どう違うのかを見ていこう。●ティーチングとの違い
ティーチングと「コーチング」の違いは考え方にある。ティーチングは上司や教師が答えや考え方、必要な知識を指し示し、部下や生徒がそれを学ぶというスタイルだ。情報の非対称性を前提としている。一方、「コーチング」は、そうした情報の非対称性は重要ではない。実際、コーチは答えを用意していない。むしろ、「答えは相手の中にある」と考える。その答えに相手が自ら気づけるよう、または一緒に見つけていくプロセスが「コーチング」となる。
●カウンセリングとの違い
カウンセリングは悩みや不安を克服・解決することが目的だ。方法としては、現状分析からスタートするが、明確な目標は設定しない。一方、「コーチング」は目標の達成・実現が目的となる。最初にどんな目標を抱いているのかを把握し、現状と理想とのギャップ、達成に必要な要素、マイルストーンなどを設定しながら目標達成をサポートしていく。●メンター制度との違い
メンター制度は、経験に基づいてレクチャーやアドバイスを行うことが目的だが、「コーチング」は相手に気づきを促し、自己実現につなげていくことを目指している。また、関係性という点で、メンター制度は上位者から下位者への一方通行となるが、「コーチング」だとコーチと相手は対等な立場となる。【関連記事】「メンター」の意味や役割とは? 制度導入のメリットや企業事例も紹介
●1on1ミーティングとの違い
1on1ミーティングと「コーチング」も目的、関係性で違いがある。まず目的としては、1on1ミーティングは上司が部下の業務に関する現状を把握・理解し、何か課題があるなら解決に向けてアドバイスをすることが目的となる。これに対して「コーチング」の目的は、相手の自己実現と成長をサポートすることにある。また、関係性について言うと、1on1ミーティングには上下関係があるが、「コーチング」はあくまでも対等な関係で進められていく。【関連記事】「1on1」の目的やメリットとは? 部下との接し方や企業事例も解説
【HRプロ】無料会員登録はこちらから >>
「コーチング」のメリット
次に、「コーチング」によってもたらされるメリットを取り上げたい。●人材育成に役立つ
「コーチング」は考える力や自主性を引き出してくれる。なので、例えば入社間もなくて職場環境や仕事の進め方に慣れていない人を「コーチング」することで、自発的な行動に繋げられる。中堅社員や管理職に対しても有効で、対話を通じて主体的に課題解決策を導き出す力や自分で考える力を養うことができる。【関連記事】「人材育成」とは? 目標や考え方、マネジメント層の育成ポイントを解説
●信頼関係の構築
「コーチング」では相手に対して質問を繰り返していくなかで、相手の考え方や価値観を引き出していく。その際に、重要なのが“承認”だ。相手の発言や姿勢を受け止め、こまめにリアクションすることで、相手は「理解され、自分を認めてもらえている」という安心感を持てる。こうした承認の積み重ねにより、部下は安心して意見を言えるようになり、上司と部下の関係だけでなく、同僚やチーム内でも信頼が深まっていく。さらに信頼関係が強化されることで、組織全体の一体感が高まり、エンゲージメント向上にもつながる。●モチベーションを向上させる
「コーチング」には短期的な効果として、対話を通じて自分の考えを整理し、目標に向けて行動するモチベーションを高める働きがある。その結果、日々の業務に前向きに取り組めるようになり、例えば営業成果の向上やプロジェクトの進捗加速といった生産性向上につながる。さらに長期的には、キャリアの方向性を主体的に描く力を養うことで成長が持続し、離職率の低下や社員エンゲージメントの向上にも寄与する。こうした成果の積み重ねが「自分ならできる」という自己効力感を高め、さらにモチベーションが高まり続けるポジティブな循環を生み出していく。【関連記事】「モチベーション」の意味や高め方とは? 部下への接し方や施策を解説
●セルフコーチングのスキルが身に付く
「コーチング」を通じて、コーチも自らの現状を客観的に分析・把握できるようになる。しかも、目標を実現する経験を一度でも得られれば、次からは「目標設定→行動→振り返り→改善」といったプロセスを自分でリードしていける。その繰り返しにより、自己管理やタイムマネジメントの力も培うことができる。メンバーが、そうしたセルフコーチングのスキルを持てるようになると主体性や学び合いの文化が根付き、チームとしてもどんどんと成長していける。●行動力・実行力の強化
コーチとの対話の中で「やると決めたこと」が明確になり、それを宣言することで日々の行動に移しやすくなる。さらに、定期的なセッションで進捗を振り返る仕組みとなるため、自分の取り組みを客観的に確認でき、改善点をその場で意識できる。この習慣が積み重なることで、実行力や継続力が自然と高まり、最終的には自走する力につながっていく。「コーチング」のデメリットと対策
「コーチング」はメリットだけではない。デメリットもある。それらを取り上げたい。●効果が出るまで時間がかかる
「コーチング」は相手に自主性を促すために、どうしても時間が掛かってしまう。ましてや、一人ひとりで課題に対する意識が違ってくるだけに、成果を導くまでのスピードも大きく異なってくる。そのため、緊急度の高い課題を解決する際には向いていないが、中長期的な人材育成、キャリア形成に有効と言える。●効果を可視化しづらい
「コーチング」は相手の内面に働きかけ、自発的な気づきや行動変容を促す手法であるため、成果を定量的に測るのが難しい。モチベーションの向上や思考の整理といった効果は目に見えにくく、周囲からは成果が分かりづらいことも多い。そのため、定性的な変化を丁寧に観察し、中長期的な成長を踏まえて評価する必要がある。●専門的なスキルが必要
「コーチング」で効果を生むには、相手の主体性を引き出す質問力や傾聴力といった専門的なスキルが欠かせない。コーチにスキルや経験が足りないと、期待通りの効果が出ず、かえって非効率的な手法となる可能性もある。社内で導入する場合は、管理職や人材育成担当者に対する研修を実施したり、外部講師を招いたりする必要があり、その分研修コストや人材育成コストが発生する点も留意しなければならない。●人によって成果にバラつきが出る
「コーチング」は、コーチと相手の関係性はもちろん、コーチのコミュニケーションスキルによって、成果にばらつきが出やすい。質問や傾聴、承認がどれだけスムーズにできるかは、人によって差があるからだ。コーチ自身のスキル研修や継続的なフィードバック、複数のコーチを比較・活用する仕組みを導入することで安定した成果につなげられる。●コストや時間的な負担がかかる
「コーチング」の制度を導入する際には、コーチを担う人材を育成するための研修コストや、学習・実践に割く時間が必要となる。また、一度導入すれば終わりではなく、継続的にセッションを行うための人員配置やスケジュール調整といった運用上の負担も発生する。そのため、効果的に定着させるには、必要なリソースをどのように確保するかが大きな課題となる。費用対効果を含めた綿密な計画が不可欠と言える。「コーチング」に必要なスキル
「コーチング」には、3つのスキルが欠かせない。それぞれのスキルについて説明していこう。●傾聴力
傾聴力とは、単に相手の話を聞くだけでなく、相手の表情や態度、しぐさなどにも気を配り、相手の感情や本音を理解するスキルをいう。傾聴力をつけることで、相手は「自分が受け入れられている」という安心感を得られ、信頼関係を築きやすくなる。その結果、相手が本音を話しやすくなり、より深い課題の発見や意識変化へとつながる。具体的には、相手の言葉を遮らず最後まで聞き切る、あいづちやうなずきで理解を示す、表情や声のトーンに注意を払い感情を読み取る、相手の言葉を自分の言葉で要約して確認するなどの行動がある。●質問力
質問力とは、相手が自ら考え、解決策を見出せるように促す質問を投げかけるスキルだ。「コーチング」で重要視されるのは「問題の外在化」であり、質問を通じて相手に自身の行動や結果を客観視させ、気づきを得られるようにすることが狙いだ。効果としては、相手が「自分の言葉」で状況を整理し、自ら答えにたどり着く過程で主体性や自己解決力が高まる点が挙げられる。具体的には、「その時どんな選択肢がありましたか?」、「もし同じ状況なら、次はどう行動しますか?」といった前向きな思考を促す質問を投げかける。また、結論を急がせず、相手に十分に考える時間を与えることも大切だ。そうすることで、本人の成長意欲と行動変容を持続させることができる。●承認力
承認力とは、相手の努力や成長に気づき、それを適切な方法で伝えるスキルを指す。承認はモチベーションを高め、安心感と自己効力感を育む効果がある。単なるお世辞ではなく、具体的な行動や成果に焦点をあてて伝えることで、相手は「自分の取り組みが正しく評価されている」と実感できる。具体的には、「期限を守って資料をまとめた点が助かった」、「前回より分かりやすく説明できていた」といった観察に基づくフィードバックを即座に伝えることが挙げられる。また、肯定的な態度を一貫して示すことで、相手は安心して挑戦を続けられるようになる。承認力は、相手の自己成長を後押しし、組織のエンゲージメント向上にもつながる重要なスキルと言える。【関連記事】「コミュニケーション能力(スキル)」とは? 種類や高める方法を解説
「コーチング」のスキルを磨く方法
続いて、「コーチング」のスキルをどう磨いていけば良いのかを説明したい。●資格の取得
「コーチング」を体系的に理解するために、資格を取得することは良い方法だ。具体的には、一般財団法人生涯学習開発財団(GLLC)後援の認定コーチや一般社団法人日本コーチ連盟(JCF)の認定コーチ、国際コーチ連盟(ICF)の各種資格などがある。●コーチングを受ける
プロの「コーチング」を受けることもお勧めしたい。どのような質問を、どんな順番で、どんな雰囲気の中で行なっているのかなどを学べるからだ。また、「コーチング」を受ける相手側の心理状態を体験できる点もメリットとなる。●セミナーや研修
企業や各種団体が開催している個人向けの説明会やセミナー、法人向けの研修などに参加し、体系的に「コーチング」を学ぶことも有益だ。講義形式だと「コーチング」に関する基本的な知識やスキルを学べるし、体験形式であればその場で実習を行い、講師からアドバイスをもらうこともできる。●読書
最近では、本屋に行くと「コーチング」について書かれた書籍が並べられている。しかも、種類もそれなりにあるので、自分のレベルや目的に合わせて購入することができる。費用も抑えられる。●eラーニング
「コーチング」は、教育事業会社などが提供しているeラーニングで視覚的に学べる。ドラマ仕立てになっていたりするので、具体的な活用方法を楽しく習得できる。また、受講者にとって都合の良い時間や場所で学習できる点も有難い。加えて、受講者個人の習熟度に合わせて自分のペースで受講できるのも、eラーニングの利点だ。【おすすめ情報】コーチングのヒントが得られるお役立ち資料一覧はこちら >>
「コーチング」の手順(GROWモデル)
「コーチング」をどのような流れで進めたら良いのか。ここでは、代表的なプロセスモデルである「GROWモデル」を題材に説明していきたい。(1)Goal:目標を明確にする
実現したい理想の状態、言い換えれば目指すゴールを意味する。「GROWモデル」では最初に相手に、この理想の状態を明確にしてもらった上でそれを実現するためにどのような目標を策定するかを考えていく。(2)Reality/Resource:現在地を認識させる/リソースを整理する
次に行うのが、現状を認識することだ。具体的には、現在の立ち位置と理想の状態とのギャップや目標達成に向けて想定される障害を相手に考えてもらう。並行して、目標を実現するためにはどのようなリソースが必要になるかも整理してもらう。(3)Options:行動の選択肢を検討する
行動の選択肢をリストアップすることを指す。どうすれば目指すべきゴールと現状のギャップを埋めることができるか、相手に挙げてもらう。その際のポイントは、制約を設けずに自由に発想してもらうことだ。自分で考えることで目標の実現に向けた意欲が高まるからである。(4)Will:意思を確認する
最後のプロセスは、取るべき行動を自ら選んで実行すると決めることだ。目標の実現に向けて抽出した選択肢の中から相手が優先順位や期限を設けて、行動計画を作り上げていく。ここでも、コーチは口を出さない方が良い。相手の自発的な行動を促していくことが重要となる。
「コーチング」で大切な3つのポイント
「コーチング」をスムーズに進めるためには、幾つかのポイントがある。ここでは、3点を取り上げてみたい。●オープンクエスチョン
「コーチング」では、相手の視点・立場に立って問いかけ、質問をすることが重要だ。それだけに、自由な回答を求めるオープンクエスチョンを用いて、相手の考えや思考を狭めず、フリーハンドで答えられるようにすることが求められる。●セカンドシグナル
部下に対して指示・命令をする際にも、「コーチング」の考え方が役立つ。具体的には、セカンドシグナルと呼ばれる手法を用いてみよう。これは、指示や命令の直後に、相手を気遣ったコメントを添えることで、相手の自発性を喚起できるという手法だ。例えば、「〜を担当してほしい」と依頼した後に、「君ならできると信じている」などと付け加えると、相手の自己肯定感を高められる。●アクノレッジメント
アクノレッジメントとは、相手を承認する、認めることを意味する。まずは、相手の存在を受け入れている、認めていると意思表示する必要がある。例えば、社内のチャットツールやミーティングでの相手の発言にリアクションしたり、積極的に話しかけたりすることが重要だ。そうした行動を繰り返していくことで、相手は「自分が認められている」と実感することができる。まとめ
ここまで「コーチング」に関して詳細に解説してきたが、最後に一点だけ補足しておきたい。それは、「コーチング」は素晴らしいマネジメント手法ではあるものの、万能ではないということだ。必ず成果が出るものではないと理解しておく必要がある。例えば、コーチと相手との間に信頼関係が構築されていない、相手が現状に満足している、コーチに経験やスキルがない…、こういった状況では成果を期待することは難しい。まずは現状を認識し、「コーチング」を導入するに相応しい状態にあるのかを確認することが重要となってくる。よくある質問
●「コーチング」の3大スキルは?
「コーチング」において欠かせないのは、「傾聴力」、「質問力」、「承認力」の3つのスキルだ。傾聴力とは、相手の話にしっかりと耳を傾けるだけでなく、表情や態度、しぐさなどにも気を配り、相手の感情を理解するスキル。質問力とは、相手に気付きを促す質問をするためのスキル。承認力とは、相手の長所や成長ぶりに気づき、言葉や態度で伝えるスキルをいう。●「コーチング」はどんな人が向いているのか?
「コーチング」に向いている人は、優れたコミュニケーション能力を持ち、人の話を傾聴できる人だ。また、人の気持ちに敏感で、相手の成長を支援することに喜びを感じることができ、寛容な思考ができる人も向いていると言える。好奇心が旺盛で自己啓発に積極的であれば、なお良い。- 1