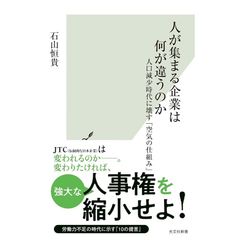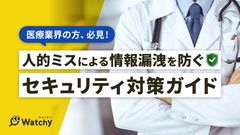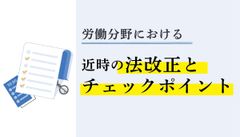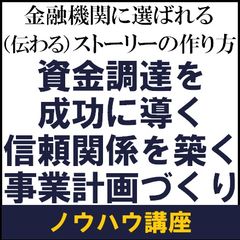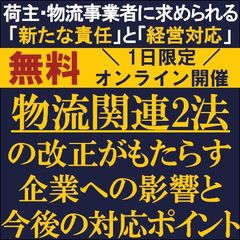■「BCP(事業継続計画)」に関するお役立ち資料はこちらから
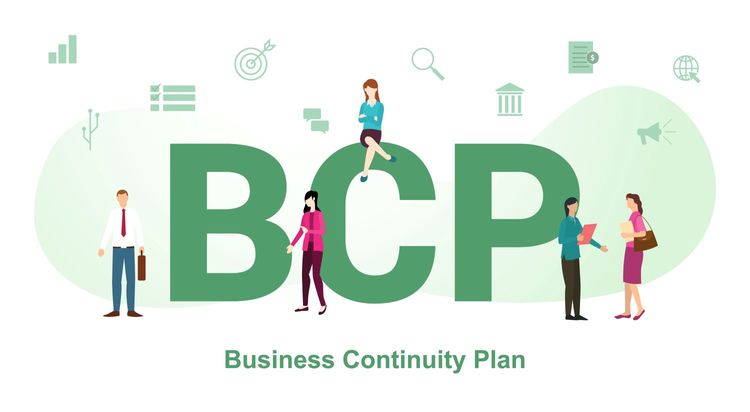
「BCP(事業継続計画)」とは
「BCP」とは、自然災害やシステム障害、テロ、ウイルス感染などの緊急事態において、企業や団体として被害や損害を最小限に抑え、速やかに事業を復旧させるために必要な方針・体制・手順などを定めた文書をいう。「Business Continuity Plan」の略称で、日本語では、「事業継続計画」と表記される。【BCPとは?】自然災害や感染症から“従業員と事業を守る”ために必要な対策を解説/社労士監修コラム集
●「BCP」の目的
「BCP」を策定する目的は、企業や団体が危機的な状況に直面した場合に、事業資産への被害や損害を最小限に抑え、重要な業務を継続するとともに事業に必要な活動の継続や早期復旧を図ることにある。●「BCP」が推進される背景
元々、日本は自然災害が多い国だ。加えて、近年ではウイルス感染症の流行やウクライナでの戦争など、自然災害以外でもさまざまな不測の事態が続いている。企業としても、いざという局面に向けた備えをしておかなければならない。日本において、「BCP」の重要性が注目されるきっかけになったのは、2011年の東日本大震災だ。それを機に内閣府がガイドラインを打ち出している。●「BCP」の策定状況
実際のところ、どれだけの企業や団体が「BCP」を策定しているのであろうか。2024年5月に帝国データバンクが行った調査の結果によると、「策定している」(19.4%)が約2割。「策定意向あり」(50.0%)は5割を占めた。また、事業継続に対して想定するリスクとしては、「自然災害」(71.1%)が最多。以下、「情報セキュリティ上のリスク」(44.4%)、「インフラの寸断」(39.6%)と続いている。BCPと近しい言葉との違い
「BCP」とよく混同される言葉に、「BCM(事業継続マネジメント)」や「防災計画」がある。それぞれの違いを解説していく。●BCM(事業継続マネジメント)の違い
BCM(Business Continuity Management)とは、事業継続マネジメントのことで、「BCP」を策定し、運用・改善していくためのマネジメントを指す。「BCP」が緊急時に事業を継続・復旧するための具体的な計画そのものであるのに対し、BCMはその計画を組織全体に浸透させ、継続的に見直し・教育・訓練を行う枠組みである。つまり、BCPは『計画』、BCMは『管理・運用』という役割分担があり、BCMの中にBCPが位置づけられる。●防災計画との違い
防災計画は、主に自然災害による被害を未然に防ぐことや、発生時に人命や財産を守ることを目的としている。避難経路の確保や耐震補強など、被害軽減のための具体策が中心だ。一方、「BCP」は災害や事故、サイバー攻撃などあらゆるリスクを想定し、重要事業の継続や早期復旧を目指す戦略的な計画である。防災が「被害を防ぐ・減らす」ための備えであるのに対し、BCPは「事業を止めない・早く立ち上げる」ための仕組みと言える。「BCP」のメリット
続いて、「BCP」のメリットを取り上げていきたい。●顧客や取引先からの信頼向上
緊急事態が起きたことで事業活動が停止した場合、その影響は当該企業だけにはとどまらない。その企業が提供する商品・サービスを購入、利用している顧客や取引先も打撃を被ってしまう。そうしたことがないよう、企業としてリスクマネジメントを徹底していると信頼度を高めることができる。●緊急時の業務継続が可能
緊急事態が発生しても、社員一人ひとりが何をすべきかを理解していると迅速な対応が図れる。その結果として、業務を継続できたり、早期に復旧させたりできるのは、「BCP」の大きなメリットだ。●被害や損失の最小化
緊急事態への初動対応次第で、復旧の時期は大きく変わってきてしまう。その点、「BCP」が策定できていると適切な初動対応が取りやすく、経営面でのダメージを最小限に抑えることが可能となる。●従業員の安全確保
緊急事態、特に自然災害時での従業員の安全確認は、その後の事業復旧にも大きく関わってくる。「BCP」を策定しておけば、災害時に全従業員の安否確認をどのように行うかが全社で共有できる。●サプライチェーン維持への貢献
「BCP」を策定することで、サプライチェーンにおいて想定されるリスクを可視化し、それらの対応策を考えることができる。緊急事態になっても、事前に準備しておいた対応策を着実に実行していくことで、サプライチェーンの維持につなげていける。●組織内の情報共有と役割の明確化
緊急事態という特殊な状況下では、さまざまな情報が飛び交い収拾がつかなくなりがちだ。また、そうした局面で情報の収集・共有を特定の人の手に委ねているだけでは、どこかのタイミングで限界を迎える可能性がある。「BCP」を策定しておけば、情報共有をどう図るか、誰がどんな役割を果たすのかが明確になるので間違った対応をする確率が低くなる。「BCP」の課題・デメリット
「BCP」には課題やデメリットがあるのも否めない。それらを取り上げてみたい。●初期コストや人的リソースの負担
「BCP」を策定するとなると、担当者の人件費やコンサルティング費用などの初期コストがかかってしまう。また、専任者を置くとなると誰に任せるかという人的リソースを講じなければいけない。社内に「BCP」に関する知識やスキルを持った適任者がいれば良いが、いないとなると外部から迎え入れることも考えなければならなくなる。●策定後の形骸化リスク
「BCP」を策定したからと言って、想定通りに機能しないことが多い。端的に言えば、想定していた以上の緊急事態が発生してしまったとか、想定外のことが起きた場合には、「BCP」は形骸化する可能性があり得る。せっかくコストを投下したとしても、何の意味もなかったということになってしまうかもしれない。●従業員への浸透の難しさ
「BCP」対策を進めていくためには、全社を巻き込んでいく必要がある。経営トップはもちろんのこと、従業員一人ひとりに浸透させ理解や協力を得ていく必要がある。ただ、これは容易なことではない。研修や勉強会なども一度実施すれば良いと言うわけにはいかないからだ。継続的な姿勢が重要となってくる。●定期的な見直し・更新の手間
「BCP」は定期的に見直していかなければいけない。社会環境や自然環境、テクノロジーなどが大きく変わってきているだけに、従来では予想もつかなったレベルの事象に遭遇する可能性があるからだ。もちろん、更新していくためには手間がかかってしまう。それを受け入れなければ、実効性の高い「BCP」を運用することはできないだろう。●リスク評価や業務選定の難易度
実際に企業が遭遇し得るリスクを見極め、分析・評価し、緊急事態においてどの業務を優先させるかを決めるのは、難易度が高い。なぜなら、その判断を誤ると「BCP」対策の効果が失われてしまうからだ。場合によっては、外部の力を借りることも考える必要がある。「BCP」策定のステップ・流れ
次に、実際に「BCP」を策定する際の具体的な流れを見ていこう。以下の6つのステップがある。(1)目的・基本方針の設定
まず、企業や団体が掲げる経営理念や事業戦略、事業目標を踏まえて、「BCP」を作ることで自社が何を目指すのかという目的や基本方針を設定する。(2)重要業務とリスクの洗い出し
次に、企業や団体にとって最も重要な業務を明らかにする。ちなみに、「BCP」では緊急事態において最も優先すべき事業を「中核事業」と呼んでいる。その上で、想定されるすべてのリスクを洗い出していく。(3)リスク評価と優先順位の決定
実際には、リソースが限られた中ですべてのリスクに対処することはできない。そこで、起こり得る事象を明確化し、それぞれのリスクを分析・評価する。その上でリスクの発生頻度と深刻度を基に優先順位を付けた上で「BCP」を策定していく必要がある。(4)対応策と復旧手順の具体化
誰が指揮を執るのか、その指示のもとでどのように行動するのかなど、対応策や復旧手順を細かなレベルまで詰め、計画書に落とし込んでいく。(5)社内共有・体制構築
「BCP」は全社で必ず共有するようしたい。いざという事態が起こったとき、経営陣はもちろんだが、現場で働く従業員一人ひとりも自発的に行動していかなければならないからだ。(6)「BCP」の見直しと改善
「BCP」は策定したままにしてはいけない。必要に応じて見直し、改善していくことがポイントだ。社内で大きな組織改編があった、中核事業に変更があった、顧客や取引先などステークホルダーに大きな変化があったなど、さまざまなケースで見直すようにしたい。「BCP」策定時のポイントと注意点
ここでは、「BCP」を策定するにあたってのポイントと注意点をリストアップしたい。●実行可能性を重視する
「BCP」策定では、最初から完璧な計画を目指す必要はない。というよりも、実際にはそれはほぼ不可能と言っていい。むしろ、完璧を目指すがために「BCP」の策定が進まず、そのうちに緊急事態に陥ってしまったとなっては何の意味もない。あくまでも、自社にとって必要なことを実行していくことに重きを置き、できる範囲から少しずつ策定を進めていきたい。「災害時の備え」で従業員の安全確保と事業継続を。BCPを策定しなくてもできる対策とは
●いつ発動するかの判断基準
「BCP」をどのタイミングで発動させるのか。その判断基準を明確にしよう。必要以上に危機意識を煽ったり、逆に危険性を軽視したりしても良くないからだ。中核事業がどんな状態になったら、緊急事態がどれほどの規模になったら、「BCP」を発動するのかを事前に決めておきたい。●チェックリストで管理
「BCP」の策定や見直しを行う際には、中小企業庁が作成したチェックリストを活用することをお勧めしたい。策定方法や運用方法などが詳細に解説されているので、自社における取り組みの現状や不足している対策などを把握しやすいと言える。●ツールやクラウドストレージの活用
どのような手順で「BCP」が策定されたのかが容易に閲覧できるとマネジメントがしやすい。そのためのツールを社内で使用していると便利だ。また、緊急事態が起きたとしても、クラウドストレージなどを活用しどこからでもアクセスできる体制にしておくと、事業の復旧を図りやすい。「BCP(事業継続計画)」対策のポイントとは? 災害時や情報漏洩のリスクヘッジのために
「BCP」の取り組み例
最後に、「BCP」の取り組み例を業種別に紹介しよう。●製造業における「BCP」対策
製造業には、原材料の調達や生産設備の稼働、製品の出荷などさまざまな工程がある。たとえ、一部の工程が停止しただけでも、全体に大きな影響を及ぼしかねない。「BCP」対策としては、以下が挙げられる。・従業員の安全確保、遠隔操作の活用
・製品の出荷ルートや物流拠点の多様化 など
●販売業における「BCP」対策
販売業では、サービスの継続性や品質の維持が欠かせない。また、店舗や物流など外部要因に左右される面もある。「BCP」対策としては、以下が挙げられる。・顧客への情報提供や対応策の周知
・販売チャネルの多様化 など
●建設業における「BCP」対策
建設業は、災害や事故などによって工事が中断されると損失が極めて大きい。「BCP」対策が重要な意味を持つ。具体的な対策としては、以下が挙げられる。・従業員の健康管理や安全教育
・協力会社や下請け業者との連携や支援 など
●自然災害に対する「BCP」対策
自然災害と言ってもさまざまな種類がある。ここでは、特に地震に対する対策を考えてみたい。具体的な対策としては、以下が挙げられる。・本社機能を代替し得る拠点の設置
・被災時の緊急通信機器やコミュニケーションツールの確保 など
●情報セキュリティに対する「BCP」対策
近年は、ランサムウェアなど情報セキュリティに関する脅威が高まっている。サーバーがダウンすることにより、企業活動に大きな支障をもたらしかねない。具体的な対策としては、以下が挙げられる。・マルウェアの検知や阻止を目的としたシステムの導入
・IoT機器に関するセキュリティ対策の強化 など
まとめ
「BCP」の策定には、当然一定のコストやリソースがかかる。しかし、現代社会はいつ、どんな緊急事態が起こり得るかわからない。想定を越えることもあるはずだ。そうした場面を踏まえて日頃から企業活動をシミュレーションしておくか、おかないかで、結果的に大きな差が生まれてしまう。想定を越えることが起きたら、次はシミュレーションで設定するレベルをさらに高める。その地道な繰り返しが、「BCP」対策においても近道となってくる。中企業庁:中小企業BCP策定運用指針
「BCP」に関するお役立ち資料、セミナー、サービスなどの最新コンテンツはこちら
よくある質問
●「BCP」とは何の略か?
BCPは「Business Continuity Plan」の略で、日本語では「事業継続計画」と訳される。自然災害や事故、システム障害などの緊急事態が発生した際、企業や団体が重要な業務を継続し、損害を最小限に抑えるための計画を指す。●「BCP」が無いとどうなる?
「BCP」がない場合、災害や事故が発生した際に適切な対応ができず、事業の長期停止や顧客流出、経営悪化につながってしまう。従業員や利用者の安全確保も困難となり、損害賠償リスクや社会的信頼の失墜、最悪の場合は倒産に至る恐れもある。●「BCP」は義務化される?
2025年4月から全ての介護サービス事業者でBCP策定が義務となり、未策定の場合は報酬減算などのペナルティが科されるようになった。一般企業では努力義務の場合が多いが、社会的要請は年々高まっている。- 1