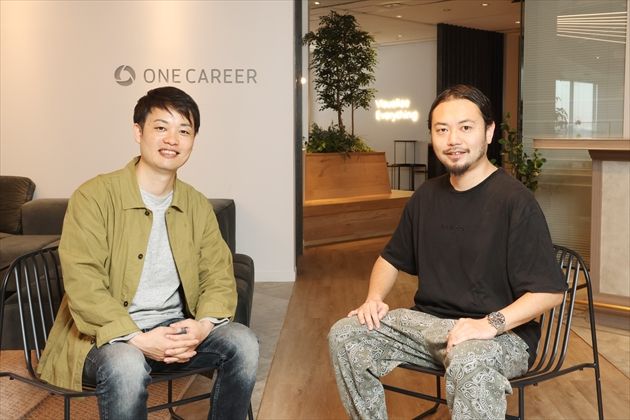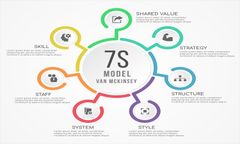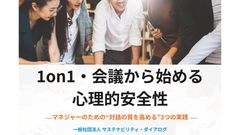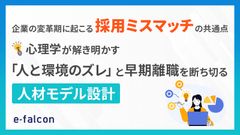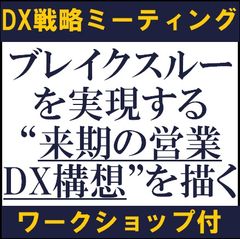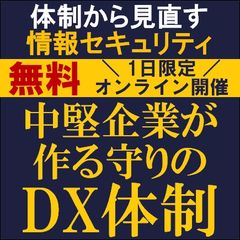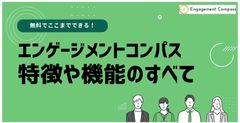寺口氏:以前の会社で、研修講師としてミドル層に向けた人材育成支援をやっていたことがあるのですが、受講者の方々のやる気があまり無かったんですね。場に意味を見出せない人たちがいる中でひたすら喋り続けるギャップがしんどくて、なんでこうなるんだろうと考えるようになりました。そのとき、自分の意思で仕事を選んでいないから、その人たちが「やらされ仕事」に陥っているのではないかと思ったんです。そこで、就職活動という一番最初の仕事選びのシーンで何が起きているのか、その領域に関心が湧きました。なので、探究心でワンキャリアに転職したようなところが少しありましたね。
三浦氏:学生時代は、サークルやゼミ、留学、起業など、自分なりにアクションを選んでいるから「やらされている感」は無いですよね。でも、就職活動の瞬間だけは急に選択肢が見えにくくなったり、どう企業を選んで良いのかわからなくなったりという感覚はありましたよね。
寺口氏:最終的には自分で選んではいるけど、ピュアな感情を邪魔するいろんなものに支配されて、「選んでる」というのがリアルかなと思いますね。その辺りの状況がすごく気になっていたんですよ。
三浦氏:今のワンキャリアでは、具体的にどんな役割やミッションを担っているのでしょうか。
寺口氏:エバンジェリストという肩書きで仕事をしています。ワンキャリアのコーポレートミッションは「人の数だけ、キャリアをつくる。」なのですが、そのために社会とどう関係構築していくかを考えて日々アクションしています。
最近携わった弊社の「いきなり最終面接(※)」という企画では、企業の最終面接に密着した様子を映像コンテンツとしてYouTubeに公開しています。今、企業説明会やインターン、社員が働く姿など、各社の想いや情報が写真や動画、記事などでオープンにされていますが、面接は最後までブラックボックスだったんです。それをオープンにしてみて世の中がどうなるかに関しては、すごく関心がありました。
ただ、動画を1本公開しても世の中のムードはつくれないんですよ。それを世の中にどう伝え、対話をつくっていくのかが大事だと思っています。企画が生まれたのが1ページ目だとしたら、そこから現在進行形で映画をつくっていくようなイメージなんです。この人がこう言ったら面白いけど、言わせることはできない。だから、その人が心の底からそのようなセリフを言ってくれるようにコミュニケーションをするんです。結局やっていることは、ムードメイキングなのかもしれないですね。
※
「いきなり最終面接」の詳細はこちらから
三浦氏:課題を投げかけて企画にするだけではなく、ストーリーも含めて組み立てているんですね。実際、企画を通して世の中にムードをつくっていく中で、寺口さんが感じている人事領域での課題はどんなことがありますか。
寺口氏:「働く」「テクノロジー」などにおいては環境の変化が速すぎて、個人と法人の間に変化対応のスピードのギャップがどんどん生まれている感覚があります。
「働く」というアジェンダで言うと、例えば、ワンキャリアの調査(※)によれば、転職を視野に入れながら就職活動をしている学生さんって4割いるんですよ。でも、新卒採用の面接で「次のキャリアパスを考えていたりするんですか?」という質問は学生にほとんどしないですよね。「働く」の主語は個人なので、企業が個人の考え方に合わせていく方が自然だと思っています。そう考えると、「早期離職はなぜ起きるのか」というのは、もはや企業だけの課題ではないのかもしれません。
「テクノロジー」というアジェンダだと、今なら「ChatGPT」ですよね。さっそく禁止している企業もありますが、これはスマホを触るなと言っていることと同じで、無理だと思います。SNSもそうですよね。「うちに入社するならSNSはダメだ」という企業もありますが、今、若い人たちにとってSNSアカウントって資産じゃないですか。メディアが個人に帰属しているにも関わらず、帰属していないものであるという前提でやっていては、もう学生に選ばれなくなっていきますよね。
現状、個人の当たり前に対する変化対応に、多くの企業が二の足を踏んでしまっています。その結果、個人から選ばれなくなっていくという構造はもともとありましたが、今すごくそのスピードが速く、課題が多いと思っています。
※
参考:株式会社ワンキャリア「就活の意識調査に関するアンケート」三浦氏:変化という意味では、今後、コロナ禍で損なわれていたものに対して新しいチャレンジをする企業が増え、企業の中でも、新たなプロジェクトを立ち上げる機会が増加していくことも想定されます。ゼロからそのような組織を立ち上げ、ムードをつくっていくときにどんなポイントが大事になってくるのでしょうか。
寺口氏:今って、一旦やってみないとわからないことが増えているじゃないですか。なので、僕は、はじめてのことは「一旦やってみる」ことが大事だと思っています。1回やると、すごくいろんなことが見えるんですよ。失敗しても多くのことを学習できる。今は「Do」と「Action」が何より大事ではないでしょうか。個人も法人も、プランニングで二の足を踏み続けている時間こそがリスクだと思うんですよ。
ただ、「一旦やってみる」ってすごく難しいんです。個人がやってみたいと思っても組織要因で止まってしまうこともあるし、組織が制度を作っても、個人に勇気がないこともある。この両方が揃わないと、個人がチャレンジできる状況はつくり得ないと思っています。個人がチャレンジしたということを歴史に残し、カルチャーとして空気に昇華させていくということが大事かなと思います。
三浦氏:個人にチャレンジを推奨する場合、どのように進めていくのが良いと思いますか。
寺口氏:僕は、「ムード」と「ルール」の、バランスと順番が重要だと思っています。ルールから出来たことって、大体しらけるんですよね。例えば、「副業制度」をつくろう、促進しようというアジェンダがあったとします。そこで、まず取り組むのは「ムードづくり」です。まず副業をしたい、やっている人を社内で探します。そして、その人たちと一緒に、どうやったら副業制度が良いものになるかを考えていく。そして、ムードをつくるために、トライアルや経験談みたいな事例を社内に出していくのですが、そのとき、組織のプロジェクトリーダーのような方は全て裏方に徹し、自然発生しているように見せるんです。そこで、ある程度ムードが出来てきたら、「じゃあ、自由に副業と言われても難しいかもしれないので、最低限のルールだけ一緒に決めていいですか?」と、ルールを決めていくんです。ルールドリブンだと、みんな疲れているので動かないんですよね。まずストーリーを仕掛けて、仕込んでおいたルールをまるで後から来たかのように置く。そうしたら、自分たちで一緒に作ったルール、制度だってなるじゃないですか。学校の校則をみんなが嫌うのは、ルールメイキングに参加していないからだと思うんですよ。会社も一緒ですよね。しらける状況が起きないようにムードもルールもデザインすべきだし、一緒に作ったルールが上手くいかなかったら、みんなでまた考えたらいいんです。
三浦氏:寺口さんが実践している、ムードをつくるためのポイントはありますか。
寺口氏:僕は、会社のみんなと喋るために毎日オフィスを散歩する時間を取っているんですよ。それで、常に2つの組織図を頭に描くようにしています。「オペレーション」と「関係」の組織図です。関係性を観察すると、意外とピラミッドの1番下の人のところにたくさん線が入っていたりするんです。ドラマの相関図のようなイメージですね。そういう人がムードのキーパーソンで、なかなか進まないことでも、その人が言ったらなぜかみんな乗り気になるんです。そういったソーシャルグラフを想像するのは大事だと思います。
三浦氏:間を繋ぐミドルの人たちにとっては、ボトムアップと同時に、トップとどう向き合うかということも大事だと思います。経営者や経営層の人たちとのコミュニケーションで、ポイントになってくることはありますか。
寺口氏:僕は肩書きに対して、偉いというより、基本的に人間対人間のフェアと捉えていますね。肩書きはあくまで役割ですし、僕の方ができることも当然あるので、びびらないです。社内のポジションを気にしている内は、経営者や経営層には相手にされないんじゃないでしょうか。ただ、経営者や経営層の方々に耳を傾けてもらうには2つの条件が必要だと思っています。
一つ目は、自分自身が意思を持って生きているか。もう一つは、その人が知らない事を知っているかどうかです。経営層だってできないことはいっぱいあるので、自分のできることであれば何でも良いんですよ。意思についてはみんな絶対あったはずなので、自分には意思が無いと諦めるのではなく、意思を思い出すという作業が大事だと思います。
あとは、BS・PL・キャッシュフローはマストで読めた方がいいです。経営者や経営層との距離が遠い人って、その方々が毎日見ている指標を読めないことが多いんです。
三浦氏:それはすごく分かります。僕も人事から経営企画部に異動してから全社や各部門のKPI、戦略議論の全体を把握する機会が増えたのですが、指標が読めることで事業責任者と対話でき、経営層とも問題点を数字ベースでコミュニケーションできますよね。
寺口氏:BS・PL・キャッシュフローを分解して、管理指標として置いているのがKPIじゃないですか。なので、上流が見えていると「このKPI、おかしくないですか?」と経営層に言えると思います。ビジネスパーソンとして生きているのであれば、ビジネスの基本ルールは押さえておきたいですね。特に、人やブランドなど、数字にあらわれにくい仕事をしている人こそ勉強した方が、経営層との距離は近くなるかもしれないです。
三浦氏:寺口さんのいろいろな考え方を知ることができましたが、これまでどのようにして自身の内面と向き合ってきたのかが気になります。最後に伺ってもいいですか。
寺口氏:いろんな方々と毎日対話をしながら、自己対話をしているんだと思います。僕は業界や職種が違う人、10代の人や60代の人とも話をします。髪を切りに行った時も美容師さんとたくさん話します。でも正直、人が好きかどうかは分からないんですよ。僕は、自分の人生がすごく大事なんです。いろんな人と対話して、どんどん人生が豊かになっていく。気づくことがある対話の相手って大事な人なんですよね。もちろん1時間話して何も気づかなかったときもありますよ。でも、常に自己対話をしながら意思を持って新しいチャレンジをしている人は、みんな、僕の人生のパートナーかもしれないですね。出会って数年経ちますが、日々試行錯誤を繰り返しながら、身の回りの人はもちろん、世の中に対しても、より良い価値を提供しようと奮闘する寺口さんの仕事に対する姿勢、結果を出しても変わらない目の前の人に対するフラットな姿勢を本当に尊敬しています。
そしてその姿勢の根っこが寺口さん自身がこれまでの人生で培ってきたものであることを今回の取材を通じて改めて実感し、勇気をもらいました。これからもきっと、泥臭く試行錯誤しながら、世の中に対してより良い価値を届け、新しい時代のムードをつくっていってくれるんだと思います。そのムードづくりに、わたし自身も少しでも伴走、支援ができればと思う取材でした。