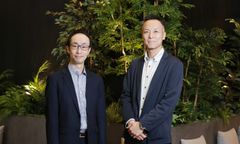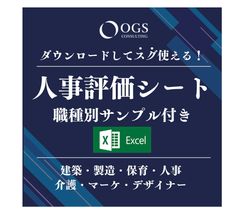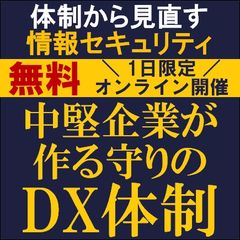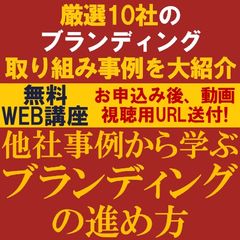低評価の社員は制度に『公平性』、『納得性』を覚えない
人事評価制度とは一定期間の社員のパフォーマンスを多面的に評価し、評価結果を処遇などに反映させる仕組みである。人事担当部門としては社員から不平・不満が出ないよう、『公平性』、『納得性』の高い制度構築に頭を悩ませるものだ。そのため、社員を客観的に評価できる評価項目を策定するなど、評価基準に『公平性』などを求めようとする取り組みが一般的である。もちろん、社員を公平に評価できる基準を構築することは重要だ。しかしながら、公平な評価基準さえ制度化できれば、納得感のある人事評価制度が導入できたと言えるわけではない。どんなに主観を交えず公平に評価できる制度を導入したとしても、低い評価を受けた社員が評価結果に『公平性』、『納得性』を感じることは稀だからだ。
それでは、社員が人事評価制度に『公平性』、『納得性』を覚えるようにするには、どうすればよいのだろうか。答えのひとつは制度の運用にある。
『公平性』『納得性』を醸成する運用上の3つのポイント
例えば、構築した人事評価制度を実際に運用するに当たり、次のような3つの運用ルールを設けたとする。このような場合には、社員は当該制度に対して「公平で納得感のある制度」との感情を抱きやすい傾向にあるようだ。(2)評価結果は期末を待たずにフィードバックする。
(3)評価期間中にマイナス評価を挽回できる指導を行う。
順を追って見ていこう。初めに、(1)の「評価基準は評価期間が始まる前に周知する」である。これは何が評価の対象かを明文化し、事前に社員に対して詳細に説明することだ。社員とすれば、評価ルールを承知の上で評価期間を過ごせるのだから、そうではないケースと比較して評価結果に『納得感』を覚える確度も高くなりやすい。
ところが、人事評価制度を設けている企業の中には、「評価基準の詳細は社員に公開しない」との運用を行っている事例も少なくない。とりわけ、中小企業では経営者の判断により、評価基準をブラックボックス化してしまうケースはよくあることだ。
しかしながら、何が評価対象になるか分からない状態で勤務をさせられた社員が低評価を受けた場合には、評価結果に『公平性』、『納得性』を覚える余地はない。
「早いフィードバック」が評価の納得性を高める
次に、(2)の「評価結果は期末を待たずにフィードバックする」である。これは評価者が評価対象となる事象を確認した場合に、社員に対して期末を待たず早めに評価結果を伝達するという運用ルールである。一般的に社員の評価は評価期間の最後に行われ、その結果が評価面談などで本人にフィードバックされる。仮に、期初に評価対象となる事象が発生した場合、評価期間が6ヵ月間であれば、社員へのフィードバックは事象発生の6ヵ月後に行われることになる。
しかしながら、何ヵ月も前に発生した出来事の評価を期末に聞かされても、社員の納得は得られるものではない。また、そもそも評価者が数ヵ月もある評価期間の出来事を、期末にモレなく誤りなく思い出すことは困難である。そのため、評価基準に合致した公平な評価が下しづらいという問題も発生するものだ。
一方、評価に関する簡易な面談を毎月2回、月中と月末に行う運用ルールとしたらどうだろうか。この場合には、評価対象となる事象が確認されてから必ず半月以内に、社員に評価結果が伝達されることになる。
評価対象となる事象の発生からフィードバックまでの期間は、短ければ短いほど社員の『納得性』は高まるものだ。そのため、社員は納得感を持って評価者の指摘に耳を傾けることが可能になるであろう。事象の発生からフィードバックまでの期間が短ければ、評価者の判断にモレや誤りが生じることも少ない。
「プラス評価に向けた指導」で社員の納得感の醸成を
最後に(3)の「評価期間中にマイナス評価を挽回できる指導を行う」は、評価結果をフィードバックする際、マイナス評価となる事象について「評価がマイナスであること」を伝えるだけでなく、「どうすればプラス評価を得られるか」までを指導することである。前述の月に2回実施する簡易な面談の際に「マイナス評価をプラス評価に変えるためのアドバイス」を受けることができれば、残りの評価期間で評価を挽回する余地が当該社員に生まれる。その結果、期末の最終評価では、プラス評価を得られるケースも生じるだろう。このような運用手法を用いれば評価制度を活用した社員のスキルアップが実現しやすいため、人事評価制度に対する社員の『納得度』も高まるはずだ。不公平感を覚える社員も少ないだろう。
しかしながら、期末までは面談を行わず、しかも期末のフィードバック内容が「マイナス点の指摘」に留まっている場合には、社員が評価期間中に評価結果を挽回する術(すべ)がない。その評価結果が処遇に反映されるのだから、社員の納得感を得ることも困難である。
納得感を高めやすい「期中の取り組み」の強化
社員に『公平性』、『納得性』を醸成する人事評価制度は、評価基準を明示した後に期中におけるフィードバックを充実させることで、一定程度の実現が可能になる。ところが、多くの企業における人事評価制度の運用は、評価期間中の取り組みが十分ではない。そのため、期末に行う評価は適切性を欠きがちであり、制度が形骸化する傾向にある。もちろん、多忙な社員に多頻度のフィードバックを求めることは、決して容易ではない。そのような取り組みに対し、「できない理由」を並べ立てる後ろ向きな社員も少なくないだろう。
しかしながら、人事評価制度を社員と企業の成長に繋げる“意味ある制度”としたければ、期中の取り組みの強化は不可欠である。「できない理由」ではなく「できる方法」を考え、ぜひとも取り組んでいただきたい仕組みと言えよう。
- 1