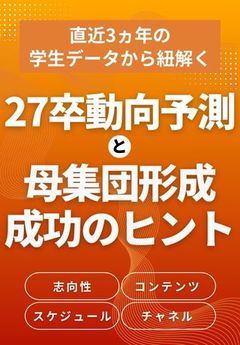障がい者雇用を進める企業が年々増え、障がいのある人とない人が一緒に働く機会が少しずつ増えてきました。一方で、障がい者社員のマネジメントを担当することになった方から、「障がい者社員の業務管理で負担が増え、自分の仕事ができない」という声を聞くことがあります。このような状況を避けるためにどのような対応が必要なのかについて解説していきます。

適切な業務設計と仕組みが不可欠
「障がい者社員のマネジメントを担当することになったが、その業務管理などの負担が増え、自分の仕事ができない」という声を聞くことがあります。この原因の多くは、適切な業務設計ができていないことにあります。障がい者社員に任せる業務を検討する時には、前任の担当者が行っていた業務をそのまま渡せないことが多いため、業務フローの見直しをする必要があったり、新たなマニュアル作成が求められたりする場合があります。それまでひとりの社員が行っていた複数のプロセスをそのまま引き継ぐのが難しい場合に、業務を分解して考えることはひとつの方法です。いくつかのプロセスに分けた時に、全てのプロセスを一任するのではなく、その中の一部を障がい者社員の業務にするということです。
業務設計の時に意識しておくとよいのは、障がい者がひとりで働ける仕組みを作ることです。障がい者にひとりで完結できない業務を任せてしまうと、確認を担当するマネージャーがその作業に時間や手間を取られ、本来の仕事に支障が出てしまう可能性もあります。また確認やチェックが必要な場合でも、いつでも質問できる状態にすると、その都度手を止めてしまうことになるため、あらかじめ業務の確認や質問の時間を決めておくとよいでしょう。
業務の簡潔化や障がいへの配慮は大切ですが、必要以上に確認やチェックに時間や手間を取られないように気をつけてください。シンプルに効率を考えたうえで、業務設計をしていきます。そして、障がい者社員に任せる業務が決まったら、これらの業務を1日、1週間、1か月と業務スケジュールに組み込んでみましょう。
定期的なフィードバックとコミュニケーションの機会をつくる
スケジュールに合わせて業務を進めていく中で、それに伴ったフィードバックも大切です。現場で一緒に働くマネージャーが「担当している業務がうまく進められているようには見えない」と思っていても、一方で障がい者社員の立場からは「一生懸命仕事に取り組んでいる」、「自分は業務がこなせている」という自己評価をしていることも少なくありません。マネジメントに携わる人と障がい者社員の間で、仕事に求められる量、質、時間などの点において大きな乖離が起こっていることはよく見られます。これらの相違を埋めていくために必要なことが、定期的な1on1(定期面談)です。業務スケジュールとともにその業務に求められる量、質、時間などの点を明確にしておくことで、お互いの考えや感覚の相違はかなり減らすことができます。合わせて、スムーズにできたのはどのような時だったのか、逆にそうでなかった時の障がい者社員の体調や気分などを振り返ることで、次に活かせる発見や参考を得られることがあります。
時には、話し合いをしている中で、作業環境の整備やプロセスを改善する必要性に気づくこともあるでしょう。そのような時には、業務のプロセスを見直したり、業務に役立つツールや環境を整えたり、教育や研修などで不足しているスキルのサポートを検討したりすることができます。障がい者社員が自立して仕事ができるような仕組みを作り、そのPDCAサイクルを回すことは、障がい者本人がひとりで業務を遂行できるようになるだけでなく、結果的に担当者の負担軽減につながります。
ミスマッチを減らすために役立つ「企業実習」
前述したように採用してから改善していくこともできますが、「こんなことが採用前にわかっていたら、もっとよかったのに……」と感じることもあるでしょう。このようなミスマッチを減らすことができるのが、採用する前に行う「企業実習」です。企業にとっては、事前に働く様子を見て人材を判断できますし、求職者側も業務内容や社内の雰囲気、状況などを事前に把握することができます。企業実習は準備に時間がかかるうえにマンパワーが必要なために、ここを省略して採用する企業も多くあります。しかし、採用して雇用関係が発生すると、途中でストップすることはなかなかできません。一方、実習では企業側も実習生もお互いを知る機会が事前に持てるので、何らかの改善が必要だとわかった時には、社内体制の見直しや整備がしやすくなります。また、短時間の面接で把握できなかったことが、実習を通して見えてくるケースが少なくありません。
面接の内容と実務で違いがあったとしても、実習を通せばそれがわかりますし、採用基準に達しているかどうかも判断しやすくなります。考えていた人材と違うのであれば、実習で円滑に終了できます。結果的に職場実習をすることで、安定した障がい者雇用に取り組みやすくなります。
例えば、業務でパソコンを使う場合に、企業が考える実務レベルと、求職者が言う「訓練機関でパソコンを学びました、使えます」というレベルとの間に大きな差が見られることがあります。障がい者の訓練機関や学校でパソコンを学ぶ機会は増えていますが、それと企業がイメージしている基準が同じであるとは限りません。このような場合でも、実習でパソコンを実際に使って実務をこなしてもらうことで、求めているレベルに達しているかどうかがわかります。
障害者雇用においては、いくらシミュレーションしたり、説明を受けたりしても、実際にやってみなければわからないことがあります。思っていたレベルに達していないこともありますし、逆に想定していたレベルよりも高いこともあります。実習中にレベルに達していないことがわかれば、プロセスを組み替えたり、マニュアルを整備したりするなどの対応が取れますし、その他の工夫で改善できそうかどうかを考えられます。また、他の候補者を検討するほうがよいのかも判断しやすくなります。
最近では、精神障がいを持った方の雇用が多くなっており、障がい者雇用における新規採用の半数は精神障がい者(発達障がい含む)です。精神障がいの場合、実務レベルだけでなく、精神的、体力的に業務を問題なくできそうかの確認も重要になります。もちろん面接では、「求める勤務時間が可能なのか」を質問するでしょうが、返ってくるのは「問題なく働ける」という答えばかりです。しかし、実際に雇用してみると、そうではない状況も多くあります。
実力よりも長い時間の勤務でも「大丈夫」という答えが返ってくる場合のほとんどは、おそらく本人も本当にその時間は働けると思っているからでしょう。実際に働いてみたら難しったというケースは少なくありません。そこで、採用前に実習をすることで、本当に事前に想定している時間の勤務が可能なのか、それとも厳しいのかも判断がつきます。また、業務のスキルや適性、障がい特性や必要とされる合理的配慮などについても、同じ職場で時間をともにすることでわかります。ぜひ採用前に実習を取り入れることをオススメします。
- 1