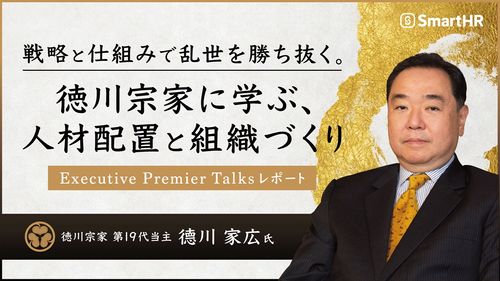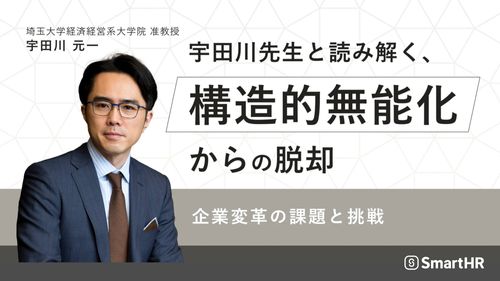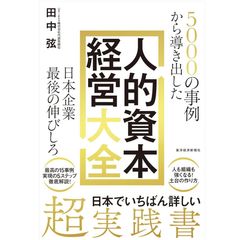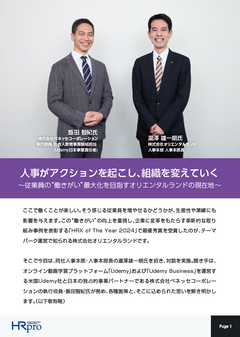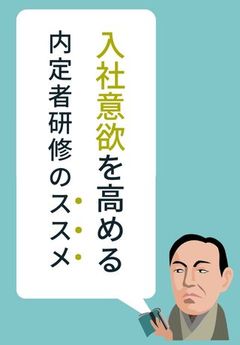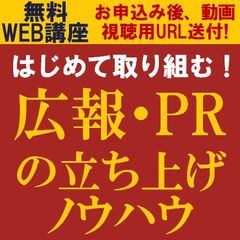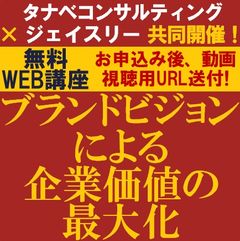「サーベイ」の意味や定義
「サーベイ」とは、物事の全体像や現状を把握するために広い範囲で行う調査を指す。一般的に従業員が自社に対してどのような認識、課題を抱いているかを調査するために活用されるケースが多い。その他では、マーケティング活動において、特定の商品・サービスに対するユーザーの印象や評価などを調べるために用いられることもある。サーベイを実施する際には、全体像を掴みやすくするため、従業員全員やなるべく多くのユーザーを対象に調査するのが望ましいとされている。●リサーチやアンケートとの違い
リサーチとは主に文献や情報を活用して行われる調査・研究を意味する。通常は、マーケティング分野で用いられることが多い。具体的には、消費者のニーズや競合他社について調べる際に行われる。対象となるのは、特定の条件にかなっている人であり、誰でも良いというわけではない。そのため、サーベイなどで全体像を把握した後、自社のコアターゲットとなるユーザーをより深く理解するためにリサーチを実施することがほとんどだ。一方、アンケートとは、多くの人に同様の質問を投げかけ回答を求める調査方法だ。企業のマーケティング活動としては、消費者やユーザーに対して行うことが多い。対象や実施方法は多種多彩。Webを活用した調査もあれば、6〜8人程度の対象者を招き、座談会形式で調査するグループインタビューなどの手法もある。
●「サーベイ」の目的
企業が「サーベイ」を行う目的はいくつかある。1つ目は、会社と各従業員の関係をしっかりと把握できること。サーベイを実施することで、従業員が思い描いている理想の組織と会社の現実との間にどの程度のギャップがあるかが見えてくる。その結果を踏まえて、会社の在り方を改善していくことができる。2つ目は、組織の隠れた課題を見出だせること。売上や利益率などの業績数字は、現在の会社の現状を表す重要な指標となるが、それがすべてではない。「次世代のリーダーが育っていない」、「部署の人間関係が悪く仕事のモチベーションが低い」といった、売上からは見えないものも拾い出していく必要がある。
このように、「サーベイ」は会社が従業員一人ひとりの意識を汲み取り、組織や体制の改善につなげていこうという取り組みだ。社内のコミュニケーションも深まるので、会社の雰囲気をより良くするきっかけとなり得ると言ってよいだろう。
「サーベイ」の種類
「サーベイ」も組織課題に応じてさまざまな種類がある。いくつか紹介していこう。●従業員サーベイ
従業員サーベイとは、従業員を対象として職場環境や、職場内での人間関係、企業と従業員との関係性などに関する満足度を把握するための調査だ。一般的には、組織改善を目的として行うことが多い。従業員サーベイを行うメリットとしては2つある。1つ目が、会社の問題点を客観的に把握できること。解決法や対応策を見出しやすくなる。もう1つが、見出した問題を解決していくことで、従業員満足度や生産性を高めていけることだ。
●組織サーベイ
組織サーベイとは、従業員のモチベーションやエンゲージメント、人間関係などを踏まえた組織状態を調査する手法だ。企業に対して従業員がどう感じているか、各部門・部署間における意識の格差がどれだけあるかなどを把握することで、組織の環境課題を明らかにすることができる。定着率の安定や離職防止につなげることができる。●パルスサーベイ
パルスサーベイとは、従業員満足度を1週間〜1ヵ月に1回といった短いスパンで、簡単な質問を繰り返して行う調査手法である。調査を頻繁に実施することで、現状の問題点を迅速に把握することができるだけでなく、変化を見つけやすくなる。そのため、主に従業員満足度の向上や職場環境の改善などを目的として実施されている。パルスサーベイを行うメリットも2つある。1つ目が、問題点や課題を見つけられ、対処や解決を図りやすいこと。従業員自身にとっても、自分を見つめ直しやすくなる。2つ目が、問題点や課題を発見・解決していくことで、より働きやすい環境を提供できるようになることだ。その結果として、エンゲージメントや従業員満足度を向上させられるだろう。
●エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイとは、自社や製品に対する従業員の愛着心を調査するものだ。従業員のエンゲージメントを調査することで、職場のどこに課題があるかを客観的な数値として洗い出すことができる。当然ながら、目的はエンゲージメントの向上となる。エンゲージメントサーベイを行うメリットは、2つある。まず、会社やチームの人事課題を客観的に把握できるために、改善へのアクションが起こしやすいこと。そして、課題に対して迅速かつ適切に対処をしていけるので、従業員のエンゲージメントを向上させられることだ。
●モラールサーベイ
モラールサーベイとは、従業員のモラールを調査する手法だ。ちなみに、モラールとは意欲や士気を意味する。その結果をもとに、どんな仕掛けをすれば、従業員が目標に対してより前向きに取り組んでくれるか、どうすればパフォーマンスが良くなるかが見えてくる。従業員のモチベーションを向上させるには重要な調査となる。●アセスメントサーベイ
アセスメントサーベイとは、従業員各々のスキルや能力を可視化することで、成長の促進や人事評価につなげる調査を言う。リーダーシップや得手不得手、職場への満足度など複合的に評価し、能力を発揮しやすい配置を行ったり、成長戦略を練ったりすることに活用できる。●コンプライアンス意識調査
これは、従業員のコンプライアンスに対する意識と、課題を把握するために実施するものだ。主に、エンゲージメントサーベイなどで用いられる心理的安全性指標などと掛け合わせることが多い。コンプライアンスに関連するリスクを未然に防げるメリットがある。●ストレスチェック
ストレスチェックとは、労働安全衛生法に基づき、2015年12月から50人以上の労働者を擁する事業場で、年1回のペースで実施が義務付けられているストレス検査を言う。目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止や、職場環境の改善だ。実際の流れとしては、まず労働者が自分のストレスに関して質問票で選択回答する。その後企業は、質問票を集計・分析し、本人に結果を通知することになっている。押さえておきたい「サーベイ」のメリット
ここでは、「サーベイ」を実施することでどんなメリットがあるのかを解説していきたい。●組織課題の数値化
「サーベイ」を実施することで、組織課題や従業員の考えを数値化することができる。その分、どのような課題があるのかが明確かつ早期に見えてくるので、改善策を練りやすくなり、組織課題の早期解決につながる。●従業員の定着率向上
従業員の定着率を向上させられるのも、「サーベイ」のメリットだ。組織における問題点・課題が客観的に把握でき、それらを改善していくことによって、働きやすさがより高まり、従業員が会社に定着しやすくなるだろう。なかでも、エンゲージメントサーベイと従業員満足度調査は結果が数値化されるため、改善に向けたアクションを起こしやすいと言える。
●サービスの質向上
「サーベイ」の結果を基にした施策により従業員の満足度が高まれば、組織全体のパフォーマンスが高まり、自ずと生産性の向上やサービスの質向上につながる。その結果、顧客満足度も得ることができる。●トラブルの予見と予防
「サーベイ」を通じて従業員の不満や懸念事項を早期に発見することで、大きなトラブルに発展する前に対策を講じることができる。特に、匿名での自由記述形式の回答からは、数値データだけでは見えてこない潜在的な問題点や普段はなかなか相談しづらいハラスメントに関する悩みなどが明らかになることもある。●変革の判断材料になる
「サーベイ」で得られたデータは、経営判断や事業戦略を練る上で重要な材料となる。サーベイの結果が、経営層の予測とはまったく異なる場合も少なくない。経営層は予想通りの結果とならなくても、その事実として受け入れ、変革すべき点を冷静に見極める必要がある。注意したい「サーベイ」のデメリット
次に「サーベイ」を実施するデメリットも紹介しよう。●従業員への負担
いざ、「サーベイ」を実施するとなると、従業員に負担をかけてしまう可能性がある。そのため、反発される可能性もあり、質問に対して何も回答しない、中途半端な回答をするといった従業員がいてもおかしくない、これでは、実施する意味がなくなってしまい、コストも無駄になる。現場の負担軽減に向けては、設問設定には留意する必要がある。●従業員からの不満
「サーベイ」を行うことで従業員から不満の声が出る可能性もある。ただでさえ、業務に追われ忙しい中、「サーベイ」のために時間を割かなければいけないからだ。また、「自分たちにとっても何か良いメリットがあるのか」、「実施する意味が見えない」といった声も寄せられるかもしれない。実施目的や期待される効果は、従業員に前もって丁寧に説明しておくいいだろう。「サーベイ」運用の流れや手順
次に「サーベイ」を運用する流れと手順を説明していく。(1)目的に応じたサーベイ設計
「サーベイ」を効果的に運用するためには、明確な目的設定が不可欠だ。何を測定し、何を解決するのか、どのくらいの期間で実施するのかを決めて、プランを立てるようにしたい。(2)データの使用範囲の決定
また「サーベイ」によって収集したデータをどう取り扱うのかを定めておく必要がある。使用目的や使用範囲、個人情報の有無、データ保存の場所など取り扱いルールは必ず事前に決めておくことで、漏洩などのトラブルを防ぐことができる。(3)社内周知と説明
「サーベイ」を実施する前には、従業員に対して周知し、その目的や意義を理解してもらうことが重要となる。なぜ行うのかだけでなく、実施による効果、結果の活用方法まで、丁寧に説明するのがポイントだ。また、「サーベイの回答結果は評価に影響しない」という点を明確にすることで、従業員が不安を抱かずに回答できる。(4)実施する
実際に実施する段階では、従業員の業務負担に配慮しつつ回答期間を設定する。またPCやスマートフォンからも回答できるシステムを活用することで、回答のハードルが低くなり、集計も容易になる。未回答者へはリマインドをして、高い回答率を確保するための工夫も必要となる。(5)結果を集計・分析
収集したデータは、全体傾向だけでなく、部署ごと、職種ごと、年齢層ごとなど、目的に応じて様々な切り口で分析したい。また、分析結果は社内で共有し、見られた課題について社内全体で認識を合わせることが重要だ。(6)改善策の立案と実行
「サーベイ」の目的はデータ収集ではなく、それを活用して職場環境や組織全体の課題を解決することである。データ収集後は、分析結果を基に具体的な改善策を立案し、実行に移していく。また、定期的にサーベイを実施することで、継続的に改善につなげることができる。「サーベイ」をうまく進めるうえでのポイント
「サーベイ」をうまく進めるためのポイントを列挙したい。●調査目的の明確化と従業員への周知
「サーベイ」を実施するにあたっては、実施の背景や「サーベイ」の目的、意義、調査結果の活用法を従業員にわかりやすく周知しておく必要がある。適切に説明することで、従業員の理解を得られやすく、その上で実施した方が、有効な調査結果を得られるからだ。●従業員の本音をヒアリングできる設計
従業員の本音をヒアリングするためには、質問設計を行う前に「サーベイ」の目的を明確化しておかないといけない。目的を踏まえたうえでの質問設計が重要となってくるからだ。また、質問を作成するにあたっては、企業の求める回答に誘導するような表現は避ける必要がある。あくまでも、公平公正な表現を使用したい。定点観測を行うために、前回と同じ質問項目をいくつか織り込んでおくことも効果的だ。●匿名回答での実施
企業内で「サーベイ」を実施する際、記名式であると従業員にプレッシャーを与えかねない。「人事評価に影響するのでは」、「自分の回答が周囲に漏れたら困る」、「上司の存在が気になる」などとどうしても考えてしまうからだ。そんな状況では、とても本音で回答してくれるはずがない。従業員の率直な意見を引き出すためにも、匿名で回答できる仕組みにすることを、ぜひ推奨したい。●一定の回答期間の確保
「サーベイ」の回答期間にも十分配慮する必要がある。どうしても、期間が短いと回答者にとっては負担になるからだ。なかには、その期間中に休暇を取っているメンバーもいるかもしれない。少しでも従業員の負担を減らすために、回答期間はできるだけ余裕を持たせたい。●回答結果のフィードバック
「サーベイ」の回答結果を人事で囲い込むのは、絶対に避けなければいけない。むしろ、従業員と積極的に共有し、「どのような課題が見つかったのか」、「それをどう改善していくのか」をしっかりとフィードバックする必要がある。情報を共有することで、初めて従業員は安心する。さらには、改善点や解決策を提示することで、従業員は自分の意見をしっかり反映してもらえたことが実感でき、今後もサーベイに対して意欲的に取り組んでくれるに違いない。これを怠ってしまえば、「サーベイ」の質は大きく低下してしまうだろう。「サーベイ」導入でよくある失敗例と対策
最後に「サーベイ」を導入する上で、よくある失敗例と対策を段階ごとに解説していこう。●設計段階での失敗
最も多い失敗は「サーベイ」の目的が不明確なまま実施してしまうことだ。職場のあるべき姿が描けていなければ、課題の優先順位を決めることが難しくなり、「サーベイ」をやりっぱなしになってしまう。その対策として、経営層を含めた組織全体で目的を共有し、「どんな結果が出ても真摯に受け止め、改善していく」という意識を持つことが重要だ。●実施段階での失敗
実施段階では、質問数が多すぎたり、回答期間が短すぎたりすることで、回答率が低下しがちだ。サーベイの目的や意義が従業員に十分に伝わっておらず、適当な回答が得られないケースもある。質問は簡潔に絞り込み、従業員の業務負担に配慮した回答期間を設定したい。●分析・活用段階での失敗
「サーベイ」の導入において最も避けたいのが、実施だけしておいて結果を放置してしまうことだ。担当者が忙しく活用まで手が回らなかったり、好ましくない結果をフィードバックするのをためらったりするなどの理由で、結果が活用されないのは非常にもったいない。結果は速やかに現場に共有するようにして、具体的な改善アクションを設定していきたい。また定期的に改善アクションの効果を測定する仕組みを整えることも重要となる。まとめ
「サーベイ」を実施することで、会社の課題が明確になり、改善策を導きやすくなるなど、さまざまな効果が期待できる。従業員のモチベーション向上はその代表格と言える。もちろん、メリットばかりではない。多大なコストと時間がかかるので、自社にとって最も効果的な方法を選ぶとともに、従業員に対して「今なぜ『サーベイ』を行うのか」といった目的を明確に伝え、理解を得ることが重要だ。また、実施後の取り組みも欠かせない。「サーベイ」を通じてどんな課題が把握できたのか、そしてそれをどう解決していくのかといった道筋を見せるとともに、実績を積んでいくことが必要だ。とにかく、やりっ放しにしてしまうことは、絶対に避けるべきだ。よくある質問
●「サーベイ」とリサーチの違いは?
「サーベイ」とは、物事の全体像や現状を把握するために広い範囲で行う調査を指す。一般的に従業員が自社に対してどのような認識、課題を抱いているかを調査するために活用されるケースが多い。一方でリサーチとは主に文献や情報を活用して行われる調査・研究を意味する。通常は、マーケティング分野で用いられることが多い。サーベイなどで全体像を把握した後、自社のコアターゲットとなるユーザーをより深く理解するためにリサーチを実施することがほとんどだ。●「サーベイ」とアンケートの違いは?
「サーベイ」は組織や物事の全体像を把握するための調査を指すのに対し、アンケートは具体的な調査手法の一つである。アンケートは具体的に、多くの人に同一の質問をして回答を求める方法だが、「サーベイ」はアンケートを含む様々な調査方法を用いて情報を収集し、分析・評価までを行う取り組みとなる。つまり、アンケートは「サーベイ」を実施する際の一つの手段として位置づけられる。- 1