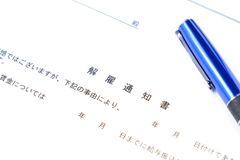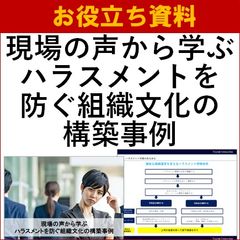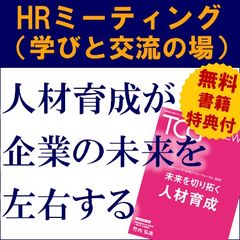人権尊重経営で問われるのは「直接の人権侵害」だけではない
人権尊重経営のプロセスで実施される人権DDでは、以下を実施することが必要とされている。… 自社に関わる「人権へのマイナスの影響」について顕在化しているリスクと潜在的リスクの両者を調査・特定し、その深刻度などを評価する。
(2)人権へのマイナスの影響の防止・軽減
… 特定された「人権へのマイナスの影響」について原因となる企業活動を停止するなどの適切な取り組みを実施し、リスクの防止・軽減を図る。
(3)取り組みの実効性の評価
… 実施した取り組みが「人権へのマイナスの影響」の防止・軽減に効果があったか、より効果的な施策があるかなどを検討する。
(4)説明・情報の開示
… 確認された「人権へのマイナスの影響」の内容や実施した取り組み、取り組みの実効性評価などについて情報を開示する。
従って、まずは(1)の「人権へのマイナスの影響の特定・評価」に取り組むことになる。
この取り組みを開始するに当たっては、企業が責任を負うべき人権へのマイナスの影響は、国連人権理事会の策定した『ビジネスと人権に関する指導原則』(通称:国連指導原則)を踏まえると、次の3パターンに分類できることを押さえたい。
2.取引先が自社の業務に関わる件で人権を侵害しており、その原因が自社にある場合
3.取引先が自社の業務に関わる件で人権を侵害しており、その原因が自社には “ない” 場合
上記2及び3にあるとおり、自社が直接引き起こした人権侵害ではなくても、責任を負うべきと考えるケースがあることを理解しておかなければならない。
自社の “過大要求” が取引先の人権侵害を助長することも
具体的に見ていこう。初めに、1番目の「自社が直接的に人権を侵害している場合」である。例えば、「製造業を営む企業が適切な安全設備を用意せず、従業員に危険な業務を担わせる」、「実施した時間外労働分の時間外手当を支給しない」などは、1番目の人権侵害パターンに該当することになる。人権侵害といえばこのパターンを思い浮かべる人が多いだろう。
次に、2番目の「取引先が自社の業務に関わる件で人権を侵害しており、その原因が自社にある場合」である。このパターンでは、自社は直接的な人権侵害行為は引き起こしていない。引き起こしたのは自社が取引をする他の企業である。ただし、取引先企業が人権侵害に走った原因が自社にあるというケースである。
具体例で考えてみよう。例えば、自社は製造業を営んでおり、取引先であるA社から必要な部品を調達しているとする。A社から見れば自社は重要な得意先である。このとき、自社がA社に対し、通常では対応困難な短納期での納品を要求したとする。A社とすれば得意先である自社の要求を断ることはできない。そのため、A社は従業員に違法な長時間労働を強いることにより、納品日に間に合わせることになったという事例である。
この事例では、「違法な長時間労働」という人権侵害行為に及んだのは自社ではなくA社である。ただし、その原因は「通常では対応困難な短納期での納品」を要求した自社にある。これが「取引先が自社の業務に関わる件で人権を侵害しており、その原因が自社にある場合」の一例だ。人権尊重経営では、このようなパターンの人権侵害にも責任を負うと考えることになる。
自社に原因がなくても責任を負うケース
最後は、3番目の「取引先が自社の業務に関わる件で人権を侵害しており、その原因が自社には “ない” 場合」である。このパターンも前述の2番目のケースと同様に、自社は直接的な人権侵害行為は引き起こしていない。引き起こしたのは自社が取引をする他の企業である。ただし、取引先企業が人権侵害に走った原因が「自社には “ない”」点で2番目のケースとは異なっている。具体例で考えてみよう。例えば、アパレル業を営む自社が、繊維メーカーB社から衣料品製造に使用する繊維を仕入れているとする。B社は原材料供給企業C社から繊維製造に使用する綿花などの原材料を仕入れている。このとき、B社では法令を遵守した経営が行われていたものの、C社では従業員に対して労働時間に応じた適切な賃金が支払われていなかったという事例である。
この事例で「賃金の支払い不足」という人権侵害行為に及んだのは、自社でもなければ自社の直接の取引先であるB社でもない。B社を介して自社との間接的な取引関係を持つC社である。また、C社の行った人権侵害行為に対し、自社は全く影響を与えていない。これが「取引先が自社の業務に関わる件で人権を侵害しており、その原因が自社には “ない” 場合」の一例である。
上記ケースでも、自社の業務に関わるところで人権侵害行為が生じたことには変わりがない。このようなパターンの人権侵害にも責任を負うと考えるのが、人権尊重経営の特徴である。
以上のように、『国連指導原則』では自社の内部における人権だけでなく、自社の製品・サービスと一定の関連を持つ外部組織の人権に対しても、マイナスの影響の防止・軽減を求めている。この点を忘れないことが肝要である。
- 1