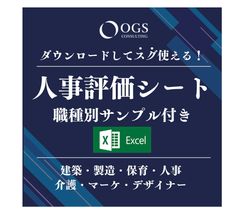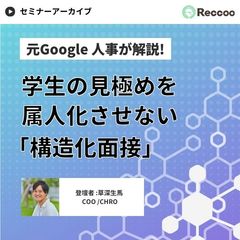「ハロー効果」の意味
「ハロー効果(halo effect)」とは、ある対象を評価するときに、その一部の際立った特徴に引きずられて、全体を歪めて評価してしまう心理現象を指す。思い込みや先入観、周囲の環境など非合理的な判断によって生じる認知バイアスの一種だ。「halo」とは天使や聖人の頭上に描かれる後光・光輪を意味する英単語だ。背後からの光が強すぎて、対象を正当に捉えられなくなってしまう様子が言葉の由来となっているため、「ハロー効果」を後光効果と表現することもある。
提唱したのは、米国の社会心理学者であるエドワード・L・ソーンダイクだ。彼は第一次世界大戦中に、上司が部下を評価する際に何らかの傾向がないかと調査。その結果、もともと優秀と評価されていた兵士は多くの項目で高い評価を得たものの、逆にあまり優秀でないと評価されていた兵士の多くは、平均以下の評価しか得られていないことに気づき、心理的な傾向があると分析した。
「ハロー効果」は、「高い評価を得やすい」、「信頼を受けやすくなる」、「マイナスのイメージを払拭できる」などの3点がメリットとしてよく挙げられる。その一方で、デメリットは、評価が歪められるといったエラーが起きやすい。
「ハロー効果」の種類
「ハロー効果」は大きく2種類に分けられる。「ポジティブ・ハロー効果」と「ネガティブ・ハロー効果」だ。それぞれについて解説しよう。●ポジティブ・ハロー効果
「ポジティブ・ハロー効果」は、対象のある一部の際立って良い特徴を捉えて、全体を実際よりも高く評価してしまう心理現象を指す。例えば、人事評価を行う際にある特定の能力やスキルが高いと、それにつられて他の項目も高く評価してしまうことがある。また、マーケティングでの事例として取り上げたテレビCMも、その効果を利用したイメージ戦略と言える。●ネガティブ・ハロー効果
「ネガティブ・ハロー効果」は、ポジティブ・ハロー効果と正反対の現象だ。対象のある一部の悪い印象に引きずられて、実際よりも全体的に低く評価してしまう心理現象を言う。例えば、人事評価において、評価者が重視する能力の評価が低い場合、別の項目もついつい低く評価してしまうことがある。また、テレビCMで起用された芸能人が不祥事を起こしてしまうとすぐに降板させられてしまう。あれも、紹介していた商品やサービスに対してネガティブなイメージを持たれることを企業が恐れるからである。「ピグマリオン効果」や「ホーン効果」との違い
次に「ハロー効果」が、「ピグマリオン効果」や「ホーン効果」とどう違うのかを説明しよう。●ピグマリオン効果との違い
「ピグマリオン効果」とは、期待をかけられた人間はモチベーションが自ずと高まり、成果が得られやすくなる心理現象を言う。米国の教育心理学者であるロバート・ローゼンタールが知能テストの実証実験を行い、期待をかけた子供らの成績がアップしたという結果に基づき提唱した教育心理学の概念だ。例えば、上司からの期待の大きな部下は、その期待通りの成果を出しやすくなると言われている。ちなみに、「ピグマリオン」とはギリシャ神話の主人公であるキプロス王の名である。彼が彫刻した女性の像に深い愛情を込めたところ、神によって生命を宿されたという逸話になぞらえて「ピグマリオン効果」と命名されている。相手の潜在的な能力や可能性を引き出すにはとても有効であり、人材育成に大いに役立つ。
このように、「ピグマリオン効果」は育成を目的とする手法であるのに対して、「ハロー効果」は評価の見え方を変えてしまう心理現象を表わしている。その点で両者は大きく異なる。
●ホーン効果との違い
「ホーン効果」は「ネガティブ・ハロー効果」と同義となる。すなわち、ある一部の悪い印象に捉われて、全体の評価にネガティブなバイアスをかけてしまうことをいう。「ホーン(horn)」とは、悪魔の角を意味する英単語だ。そのため、「ホーン効果」は別名、悪魔の角効果と称されることもある。「ハロー効果」は聖人の後光であり、「ホーン効果」は悪魔の角と表現することから、この二つは全く対極にあることが容易に理解できることであろう。「ハロー効果」の具体例
実際に、「ハロー効果」としてどのような例があるのか。人事評価や採用面接などの人事領域、マーケティング領域、その他の身近な例に分けて見てみよう。●人事評価
ソーンダイクの分析結果にもある通り、人事評価では「ハロー効果」が顕著に出やすい。実際、ある一部の評価が高いとそれに影響され全体的に高い評価を付けてしまいがちだ。逆に、ある一部の評価が低ければ、その印象に引きずられてしまい全体を低く評価しがちである。●採用面接
採用面接を行う際に、応募者の学歴や容姿、面接官との共通点などの目立つ特徴に引きずられ、知らず知らずのうちに評価にバイアスをかけてしまうことがある。また、第一印象の良さに引きずられるというケースもある。反対に、際立った特徴がない、面接官と特に共通点もないとなると、全体的に評価が下がり気味となってしまう。いずれも、「ハロー効果」がもたらす現象と言える。こうした評価をしてしまうと、採用の本質から逸れてしまうのは言うまでもない。●マーケティング
マーケティングでも、「ハロー効果」を多用している。例えば、テレビCMで好感度の高いタレントやルックスの良い有名人を起用するのも、「ハロー効果」を狙ったものだ。「あの人が勧める商品であるなら信頼できる」、「憧れの○○さんが言うなら、良い商品に違いない」などと無意識のうちにポジティブに受け止めてしまうものである。●その他の身近な例
「ハロー効果」は日常的に見られる。自信に満ちた態度で行われたプレゼンテーションは、内容自体の評価も高めてしまったり、営業担当者の身だしなみや話し方が良いと、提案内容や製品の評価も高くなる傾向があったりする。企業のホームページに笑顔で働く従業員の写真を掲載することで、店舗の雰囲気や商品の品質まで良く見せる効果もある。有名企業との取引実績があると、その会社全体の信頼性が高く評価されるのも「ハロー効果」の表れである。「ハロー効果」以外の評価誤差や心理的傾向
実は人事評価を行うにあたり、「ハロー効果」以外に留意しておきたい評価誤差や心理的な傾向がある。いずれも、評価者の主観によるもので評価に大きな隔たりをもたらすだけに、しっかりと理解しておくようにしたい。●中央化傾向
「中央化傾向」とは、非常に優秀、非常に劣っているという極端な評価をあえて避け、無難な中央値に集中させてしまう傾向を指す。5段階評価であれば、評価者は5や1を避け、中央値の3に評価を集まる状態を言い、「中心化傾向」と称されることもある。こうした心理作用が起こる理由としては、「被評価者から嫌われたくない」「被評価者を観察していない」「評価者に自信がない」などが考えられる。いずれも、適正な評価はできていないので人事評価において問題となる。
●寛大化傾向
「寛大化傾向」とは、厳しい評価を避け評価が全体的に甘くなってしまう評価誤差を言う。5段階評価であれば、評価者は5や4ばかりを付けてしまう現象だ。結果として、評価の差が出にくくなるだけでなく、下位評価を受ける者も少なくなる。これは、評価者が「被評価者を気遣ってしまう」「被評価者から良い印象を持たれたい」「自分のスキル・実力に自信を持てない」などの気持ちから起きることが多い。ただ、実態にそぐわない評価をしてしまうと、かえって相手の成長を阻害する恐れがあるので注意を要する。
●厳格化傾向
「厳格化傾向」とは寛大化傾向とは逆で、実態よりも厳しく評価することを言う。評価者が高い基準を持っていたり完璧主義であったり、「甘い評価者と思われたくない」という意識があったりすることから生じる。良い点よりも欠点に注目し、実際の能力や成果よりも低い評価をつけがちのため、モチベーション低下や不公平感を生み出し、人材育成や組織の成長を阻害する要因となり得る。●逆算化傾向
「逆算化傾向」とは、評価者が優良な評価に落ち着かせるために、最終評価から逆算してそれぞれの評価項目のつじつまを合わせてしまう傾向だ。5段階評価で、評価者が最終的な評価を3にしたいと決めていた場合、平均が3になるように数字を組み合わせてしまうことを指す。当然ながら、実際の評価と一致しなくなる可能性が高い。これは、評価者が「チーム全体の評価を底上げしたい」「評価について文句を言われたくない」などと打算的に思っているケースで生じやすい。「逆算化傾向」を防ぐには、「評価基準を明確にする」「複数の人間が評価する」「評価と処遇をリンクさせない」などの施策を講じる必要がある。●分散化傾向
「分散化傾向」とは、わずかな差や些細な問題を拡大解釈して評価しまうことを言う。前述の「中央化傾向」とは正反対の評価傾向であり、「二極化傾向」や「極端化傾向」と呼ばれることもある。この傾向に陥りがちな上司に共通している特徴としては、「部下を日頃からしっかりと観察していると思いこんでいる」「部下の評価にあえて差を付けることで、部下のモチベーションにスイッチを入れたい」などが窺える。ただ、その結果として評価にばらつきが生じるばかりか、評価と実態に乖離があり正当とは言えないなどの問題が起こる可能性が高い。
●論理誤差
「論理誤差」とは、評価者がファクトベースでの論理的な分析・判断をせず、独りよがりの考えや憶測、推論で評価してしまう誤差を指す。出身大学や評価者の価値観などを優先することもその表れだ。例えば、採用面接で応募者の履歴書に「競技スポーツの経験あり」と書いてあるだけで、「協調性があり、仲間を大切にする」「忍耐力がある」と勝手に判断しがちである。また、「営業部門で活躍していた」と聞くだけで「話し上手なのであろう」「押しも強いはずだ」などと決め付けてしまうこともある。●対比誤差
「対比誤差」とは、絶対的な基準ではなく、評価者自身やある特定の人物を評価の基準として、相対的に能力評価をしてしまうことで生まれる誤った評価を言う。評価者自身が得意とする項目には厳しく、逆にあまり得意でない項目にはついつい甘く評価してしまう。それだけに、被評価者が評価者自身と同様の行動特性を持つ、ないしは正反対の行動特性を持つ場合には、実際よりも過大あるいは過小評価をしてしまうので、注意を要する。
●期末誤差
「期末誤差」とは、期末での印象的な行動や出来事を重視してしまい、全体を正しく評価しない傾向を意味する。例えば、評価期間の半ばあたりまでは仕事でミスを繰り返していたとしても、期末に大きな契約を獲得した際や、会議中に一切発言をしなかったが、最後にインパクトのある提言をした場合、その印象の強さから高い評価を与えがちだ。もちろん、逆のケースもあり得る。安定して高い売り上げを維持していたが、最終月に売り上げを大きくダウンさせた場合や、会議中に幾度となく発言していたが、最終的には別の人の意見が採用されたケースであれば、直近の悪い印象に引きずられ評価を落とすことが多くなりがちだ。人事評価での評価エラー防止策
人事評価における評価エラーを防止するにはどうすればいいのか。対策として以下のような方法がある。●評価基準の明確化
評価エラーを防ぐためには、まず評価基準を明確にすることが重要である。誰が評価しても一定の評価となるように、項目と基準を明文化して社内で共有するべきだ。評価基準が曖昧だと評価者の裁量に委ねられるため、どうしても評価エラーが発生しやすくなる。明確な基準があれば、評価者の個人的な感情や主観に左右されない。また部下が疑問を抱いた際も理由を説明しやすくなる。●評価者研修の実施
評価者に人事評価制度の内容や基準を理解してもらうには、評価者研修を実施するのが有効だ。人事評価にはさまざまな誤差や心理的傾向が発生しやすいことを理解してもらい、公正な人事評価の方法や注意すべきポイントを学んでもらえる。●複数評価者による評価
評価エラーの影響を軽減するには、複数体制での評価が効果的だ。一般的に「自己評価」、「直接の上司評価」、「部門長の評価」と段階を踏んで評価を確定する方法や、360度評価など多角的な視点からの評価を取り入れることで、評価者個人の偏りを防ぐことができる。●具体的事実に基づく評価
被評価者のイメージや固定観念が評価に影響しないよう、具体的な事実や行動に基づいて評価することが重要と言える。日頃の社員の仕事ぶりを記録するなどして、行動事実を評価へ反映すると良いだろう。●評価のフィードバック
部下に対して評価結果だけでなく、具体的な理由も加えてフィードバックすることが評価エラーの防止につながる。自分の感覚に依存していないことを説明できるとともに、被評価者の納得度が高まり不満の軽減にもつながる。●コンピテンシー評価の導入
優秀な人材に共通するコンピテンシー(高い成果につながる行動特性)を明確にし、評価の基準とすることで、定量的に評価をすることができる。定性的な印象評価がなくなり、基準のブレが少なくなるのだ。●評価者同士の基準すり合わせ
評価基準を明確にしたあとは、評価者同士ですり合わせを行うことも大切だ。評価項目や基準について評価者同士で共通理解を持つことで、評価の一貫性を高めることができる。
まとめ
確かな基準があれば評価もしやすいが、実際には自分自身の思い込みや先入観で評価してしまうことがある。特に難しいのが、人に対する評価だ。誤った判断は、組織に大きなマイナスをもたらす。そうした誤りを防ぐためにも、「ハロー効果」を含め、どのようなケースで評価誤差が生じやすいのかを理解しておくのは重要だ。しっかりと学んでおけば、採用面接や人事評価などのシーンで効果的に活用することもできるだろう。同時に、「ハロー効果」の悪い影響を避け、対象の特徴を的確に評価する心がけも欠かせない。メリット、デメリットを鑑みて、上手く使い分けるようにすることが重要だ。「評価制度」に関するニュース・サービス・セミナー・資料請求などの最新情報はコチラ
よくある質問
●「ハロー効果」の具体例は?
「ハロー効果」の具体例として、営業担当者の身だしなみが良いと提案内容も高評価になったり、有名大学出身者の仕事を実際より高く評価してしまったりすることが挙げられる。また、プレゼンテーションでの堂々とした態度が内容の評価を高めたり、人気タレントが起用された商品の品質を無意識に高く判断したりする現象も日常的に見られる。●ウィンザー効果とハロー効果の違いは何?
ウィンザー効果とは、ある人物の優れた特性が他者の評価を下げる現象で、比較による相対評価のバイアスを指す。一方、ハロー効果は一人の人物の特定の良い特性が、その人の他の特性まで良く見せる現象を言う。つまり、ウィンザー効果は「他者との比較による評価の歪み」、ハロー効果は「一人の人物内での評価の波及」という点で異なる。- 1