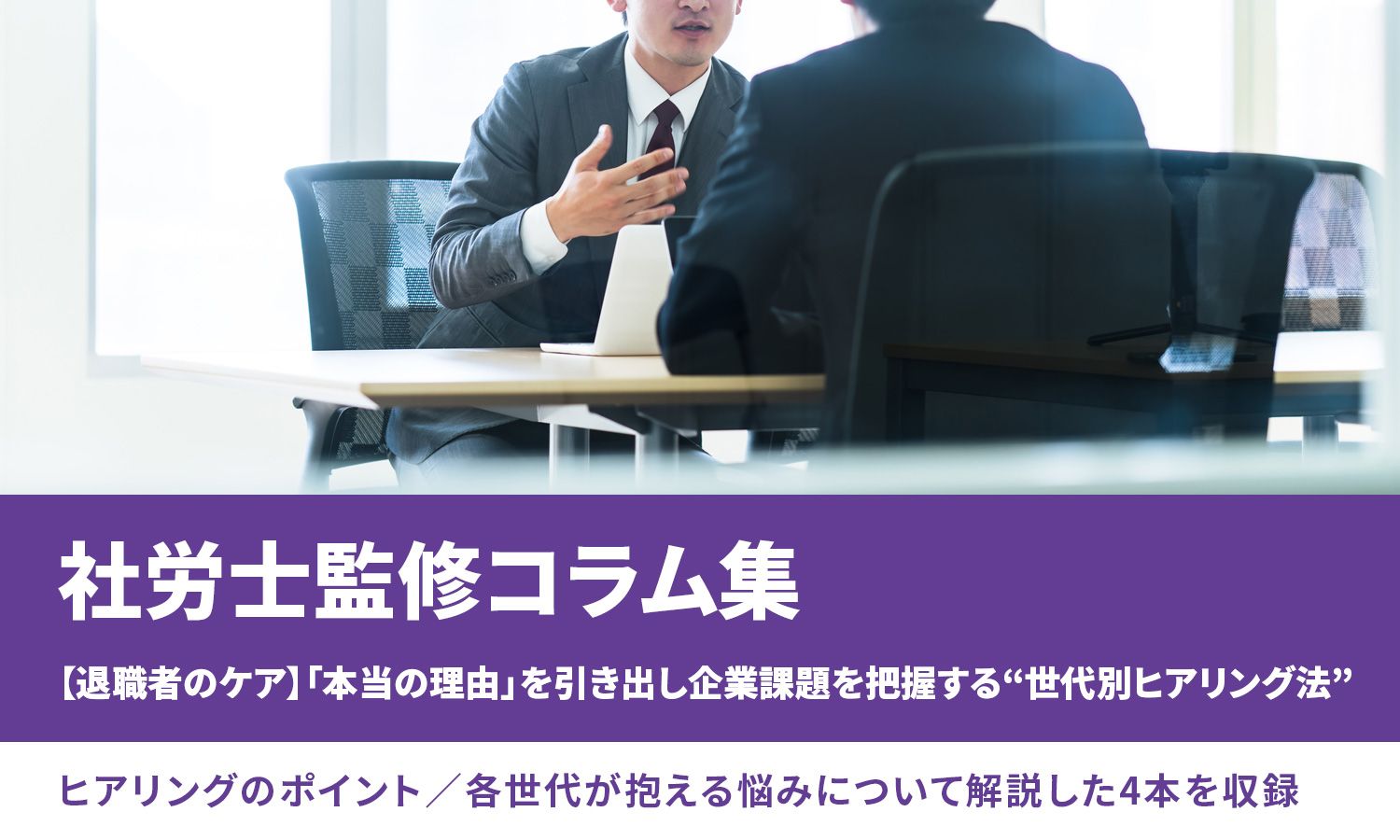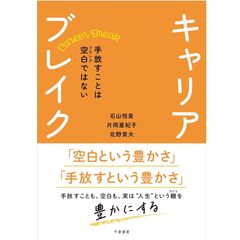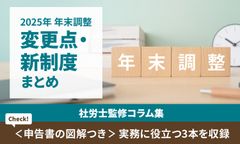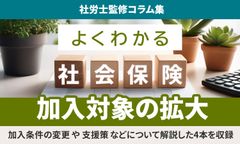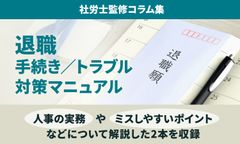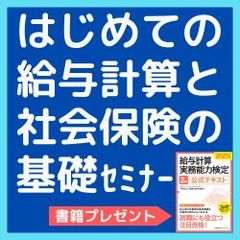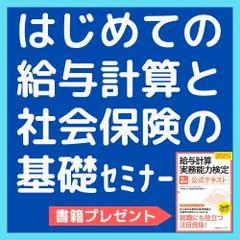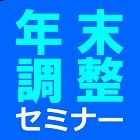1:退職金や社会保険はどうなる? 社員から「退職の申し出」があった場合の手続きとは
※関連情報を記載した資料も公開中
【退職者のケア】「本当の理由」を引き出し企業課題を把握する“世代別ヒアリング法”/社労士監修コラム集

1)年次有給休暇の処理:余った有給休暇の買い取りは必須? 違法?
年次有給休暇(以下、「有給休暇」という)が残っている場合、その残日数の処理をどのようにするのか退職者本人と決める必要があります。処理方法は3つです。(1)退職日までに取得してもらう
引き継ぎ業務との兼ね合いも考えながら、退職日までに有給休暇を取得してもらいます。それでも取得しきれない場合は、次の(2)(3)の扱いになります。(2)買い取る
通常は、会社が有給休暇を買取りすることは違法です。有給休暇は心身を休めることが目的のため、休むことが必要で、お金で解決することはその制度趣旨に反するからです。しかし、退職時あるいは時効によって消滅する有給休暇に限っては、制度趣旨に反することがなく、有給休暇の買取りは違法ではありません。買取りをするかしないか、買取りをする場合でもその金額をいくらにするのか等は、会社の任意です。
(3)何もせず消滅
有給休暇の残日数について何もしないパターンです。有給休暇は、在職期間中に権利が発生するため、退職すると有給休暇権は消滅します。そのため、上記(1)や(2)の対応をせずにそのまま退職日を迎えると、有給休暇は消滅します。2)誓約書:退職後のトラブル防止に「5項目」を盛り込もう
退職時には誓約書を退職者に提出してもらいましょう。目的は、企業の機密情報や取引先情報の保護、競業避止義務の確認、退職後のトラブル防止のためです。誓約書には次の項目を盛り込むとよいでしょう。(1)機密保持義務
「私は在職中に知り得た会社の営業機密、技術情報、顧客情報その他の機密情報を退職後も一切開示、漏洩、使用しません。」(2)競業避止義務(必要に応じて)
「私は退職後、会社が指定する期間(例:1年間)、同業他社に転職したり、御社の競争相手となる事業を行ったりしません。」ただし、競業避止義務は合理的な範囲(期間・地域・職種など)で設定しないと無効になる可能性があるので注意しましょう。労働者には憲法で保障された職業選択の自由があるからです。
例えば、システムエンジニアとして働いていた元従業員との「競業避止義務」に関する合意について、制限期間が1年間にとどまっているとしても、転職先の地理的範囲は制限なく、転職先も元会社と関係がある会社まで広範で、必要かつ合理的な範囲を超えていることから、この合意は公序良俗に反し無効とされた事案があります(東京地裁令和4年5月13日判決「REI元従業員事件」)
(3)会社資産の返却義務
「私は退職に際し、会社から貸与された物品(PC、スマートフォン、IDカード、書類など)をすべて返却し、データを私的に保持しません」(4) 取引先・顧客の勧誘禁止
「私は退職後、会社の取引先、顧客、従業員に対し、直接または間接的に勧誘や引き抜きを行いません。」(5) 損害賠償責任
「もし本誓約書に違反した場合、会社に生じた損害を賠償する責任を負うことを理解しました。」最後に、退職者の氏名、退職日を記載の上、本人の署名等をもらいます。
3)退職後の「健康保険」の給付手続き:出産や長期療養の手当てはどうなる?
退職者が出産を控えていたり、長期療養による傷病手当金を受給していたりする場合、一定の条件を満たせば退職後も継続して受給が可能です。退職後の手続きなので、退職者本人が直接協会けんぽ等の保険者に申請します。会社は手続きに直接関与しませんが、退職者がスムーズに申請しやすいように支給要件や申請の流れなどを説明しておくとよいでしょう。(1) 出産育児一時金(50万円)
退職者本人(被保険者)が、退職前に健康保険に1年以上加入 し、退職後 6ヵ月以内に出産すれば、退職前の健康保険から支給されます。ただし、退職後に配偶者の健康保険に扶養として加入すると、そちらから支給されます。退職後の給付はあくまで被保険者であった人の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。また、退職後に国民健康保険に加入している場合、そちらからも支給されますが、健康保険と国民健康保険の両方から受給することはできません。どちらか一方を選択することになります。
(2) 出産手当金(産休期間の所得補償)
出産手当金は産前6週(42日)、産後8週(56日)の合計98日分の産休中の所得補償として健康保険から支給されます。この出産手当金は、退職時に出産予定日前42日以内 に入っており、1年以上健康保険に加入していた場合、退職後も受給できます。退職日の時点ですでに出産手当金を受けているか、申請していなくても支給条件を満たしていることがポイントです。
なお、退職日に出勤したときは、出産手当金を受けられる要件である「労務に服さない状態」に該当しないため、退職後の出産手当金は受給できません。そのため、退職の当日に出社するとしても、貸与物の返還等、事務手続きのみで済ませるべきです。
(3)傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際に給与の代わりとして最長1年6ヵ月の間支給される健康保険の給付です。長期療養が必要な場合、会社に休職制度がある場合にはそれを利用することになりますが、中小企業ではそもそも休職制度がなかったり、休職期間が1年未満であったりすることが多くあります。休職期間が終了すると、自然退職や解雇となることがほとんどであるため、退職後の傷病手当金はとても大切な制度といえます。
退職後に傷病手当金を受け取るには、退職前に1年以上健康保険に加入しており、退職時点で傷病手当金を受給中、または支給条件を満たしていることが必要です。また、退職後も働けない状態が続いていることが条件となります。
- 1