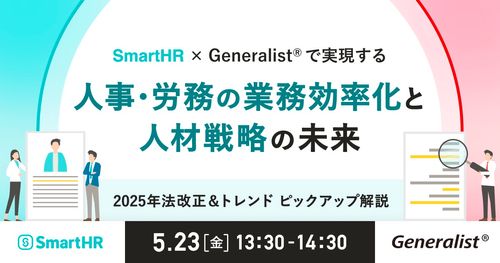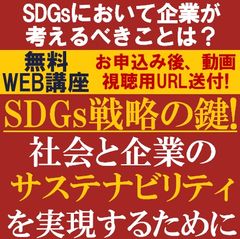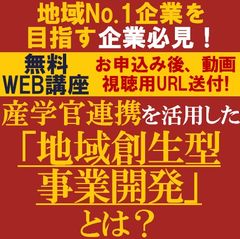■「CSR」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら

「CSR(企業の社会的責任)」とは
「CSR(Corporate Social Responsibility)」とは、企業が事業活動を進めていくにあたり、地球環境や次世代に配慮するとともに、顧客や従業員、株主、地域社会などに対して常に責任ある行動を取り、説明責任を果たしていくべきであるという概念だ。日本語では「企業の社会的責任」と訳される。●「CSR」における7つの原則と7つの核心主題
国際規格「ISO26000」では、「CSR」における「7つの原則」と「7つの核心主題」を掲げている。「7つの原則」
「7つの原則」とは、企業が社会的責任を果たすための基本方針だ。国際規格「ISO26000」では、以下が掲げられている。(1)説明責任
企業活動が社会に対して与える影響を十分に説明する。
(2)透明性
意思決定や企業活動の透明性を保つ。
(3)倫理的な行動
倫理観に基づいて企業活動を行う。
(4)ステークホルダーの利害尊重
様々なステークホルダーに配慮して企業活動を行う。
(5)法の支配の尊重
事業活動を行う国や地域の法令に順守する。
(6)国際行動規範の尊重
法令のみならず、国際的に通用している規範を尊重する。
(7)人権の尊重
人権を尊重する。
「7つの核心主題」
「7つの核心主題」とは、企業が社会的責任を果たすために具体的に取り組むべき主要なテーマや領域を言う。国際規格「ISO26000」では、以下が示されている。(1)企業統治
内部統制の強化、公正な意思決定・運営
(2)人権
児童労働の禁止、ダイバーシティの推進
(3)労働慣行
労働環境の改善、従業員の健康管理
(4)環境
省エネ、二酸化炭素の削減
(5)公正な事業慣行
コンプライアンスの尊重、公正な競争
(6)消費者課題
消費者のプライバシー保護、品質管理や情報開示
(7)コミュニティへの参画
地域社会との連携、ボランティア活動
●「CSR」が注目されている背景
日本において「CSR」が注目された背景には、2000年以降企業の独善的な行動や不祥事が立て続けに起き、社会からの信頼が大きく低下したことがある。失った信頼を回復するためにも、大企業を中心に「CSR」を適切に果たす重要性が広く認識され、経営理念やビジョンなどに取り入れる動きが広がった。コンプライアンス意識の高まりもあって、最近では大企業だけでなく、中小企業でも「CSR」に取り組む企業が増えている。日本と海外における「CSR」の違い
日本と欧米では「CSR」の認識が異なる。どう違うのかを説明したい。●米国との「CSR」の違い
米国は「CSR」の先進国だ。1990年代後半から多くの企業がCSRの活動を推進するようになり、2000年代には、グローバル化によって発展途上国の労働者を雇用する動きが活発化し、CSRの法整備が進んだ。米国企業は日本企業よりも総じて企業規模が大きいだけに、「CSR」関連にかなりの予算を割り当てている。年間で数千億レベルという企業も珍しくない。また、「CSR」に関する投資家の関心も高い。それだけに、「CSR」に積極的な企業は、日本以上に企業価値が高いと見られている。
●ヨーロッパとの「CSR」の違い
一般的に、ヨーロッパではEUにおける意思決定に準拠して自国の政策的取り組みを策定する傾向が強い。「CSR」に関しても同様だ。2001年にEUが発表した「CSRのための欧州の枠組みの促進」というグリーンペーパーによって重視されるようになった。このグリーンペーパーは、長期的な経済成長を目指すために策定された「リスボン戦略」の一環として位置づけられ、その中でCSRが重要な要素だと考えられている。そのため、EU加盟国の間で、「CSR」の活動についてもほぼ足並みが揃っている。一方、日本では国際協調の観点を踏まえながらも、基本的には自国の状況に照らし合わせて「CSR」に関する方針・施策を策定している。
「CSR」と関連用語との関係性・違い
「CSR」には関連した言葉や近しい概念が多くある。それぞれの関係性と違いを説明していこう。サステナビリティとの関係性・違い
サステナビリティは、環境・社会・経済のバランスを保ち、将来世代にわたって持続可能な社会を実現するための考え方だ。「CSR」は企業が社会的責任を果たすための活動全般を指し、その中にはサステナビリティの実現も含まれる。つまり、サステナビリティは「CSR」の重要な要素の一つであり、「CSR」の枠組みの中で追求される目標と言える。SDGsとの関係性・違い
SDGs(持続可能な開発目標)は、国連が定めた2030年までの「持続可能な開発目標」のことを言う。「CSR」は企業が自主的に社会や環境へ配慮する活動全般を指すが、SDGsは国家や企業、個人を含めた全世界共通の達成目標だ。CSR活動はSDGsの達成に貢献することが期待されるが、「CSR」は企業独自の社会貢献活動、SDGsは国際的な指標という点で違いがある。「SDGs」の17の目標とは? 企業が取り組むメリットや事例を解説
ESGとの関係性・違い
ESGは「環境(Environment)」、「社会(Social)」、「企業統治(Governance)」の3要素を重視し、企業の持続可能性や社会的責任を評価するための具体的な基準だ。「CSR」が企業の社会的責任や倫理観を示し、社会や環境への配慮を「責任」として捉えるのに対し、ESGは環境・社会課題への対応を経営の中心に据え、企業価値向上と両立させるものである。また、ESGは投資家による企業評価の指標としても活用され、企業の長期的な成長や持続可能性を重視する枠組みである点も「CSR」と異なる。「ESG」とは? 意味や注目される理由からESG投資の種類や事例まで幅広く解説
CSVとの関係性・違い
CSV(Creating Shared Value)は、事業活動を通じて社会課題を解決しつつ企業価値も高める経営手法だ。「CSR」が社会的責任を果たすための活動全般を指すのに対し、CSVは社会的価値と経済的価値の両立を目指すものである。ボランティア活動との関係性・違い
ボランティア活動は、個人や団体が無償で行う社会貢献活動を言う。一方で「CSR活動」は、企業が社会的責任を果たすために行う活動全般であり、有償・無償を問わない。「CSR」の中にボランティア活動が含まれる場合もあるが、「CSR」はより広い範囲の社会貢献や責任ある企業行動を指している。コンプライアンスとの関係性・違い
コンプライアンスは法令や社会規範を遵守することを意味し、違反すれば法的制裁を受ける可能性がある。「CSR」は法令遵守に加え、社会や環境への自主的な配慮や貢献も含む広い概念だ。つまり、コンプライアンスは「CSR」の一部であると言える。「コンプライアンス」の意味や違反の事例、必要な取り組みとは?
「CSR活動」のメリット
次に、「CSR活動」に取り組むメリットを取り上げたい。●企業イメージ・信頼度の向上
「CSR活動」のメリットのひとつが企業のイメージアップだ。「CSR」を推進している企業は、環境に配慮している、人権を重視していると捉えてもらいやすい。その結果、取引先や消費者からの信頼度がますます高まり、業績にも良い影響がもたらされる。●従業員のモチベーション向上
「CSR活動」に積極的に取り組んでいる企業では、従業員が社会貢献を実感しやすい。そうした環境だと、職場への満足度が高まり、モチベーションやエンゲージメントも向上する。自分が在籍する組織が社会的責任を果たしていると認識できると、従業員は自分の仕事に誇りを持てるからだ。●人材の確保・定着
「CSR」活動によって信頼度が向上すれば、企業経営も安定する。自ずと、従業員の待遇を改善したり、福利厚生の充実、労働環境の改善などを行う資金的なゆとりも確保しやすくなったりする。結果として、従業員はもちろん、求職者からも好感を得られることになるので、人材の確保や定着を実現しやすい。●コンプライアンス違反の低減
「CSR活動」に取り組んでいくと、自社の企業活動に関するコンプライアンス・チェックを行う機会が増える。そのため、法令違反があった場合には速やかに事実確認ができるだけでなく、原因の早期解明・是正も図りやすい。不祥事によって社会的評判が傷つくリスクを低減することもできる。●ステークホルダーとの関係強化
「CSR活動」を行うことで投資家や株主、顧客、取引先などのステークホルダーと良好な関係を構築でき、ビジネスを円滑に運営していきやすくなる。「CSR活動」のリスク
企業が「CSR活動」に取り組むことに関してはリスクも想定される。具体的に説明していこう。●コストがかかる
「CSR活動」は、長期的なスタンスで取り組む必要がある。短期で業績アップにつなげるのは難しいと言える。しかも、「CSR活動」を行うには、人件費をはじめ様々なコストが生じてしまう。それを承知の上で、「CSR活動」に向き合っていくには、企業としてそれ相当の体力が求められる。●従業員に負荷がかかる
従業員からすると、「CSR活動」は日々行っている業務とは関係性が薄い。むしろ、追加の作業をしているという負担感を抱かせてしまう可能性がある。●生産性低下の恐れがある
実は、「CSR活動」に注力することで生産性が低下する可能性がある。ストレートに、売上・業績の向上に力点を置いた方が、短期的には業務効率が良くなると言える。あくまでも長期的な観点、将来につながる投資と捉えることができるかどうかが鍵となる。【7つの主題別】「CSR活動」の取り組み例
企業が「CSR活動」に取り組む際には、会社の状況に応じて検討しなければいけない。国際規格「ISO26000」で示されている7つの主題別に取り組み例を紹介していこう。●企業統治
企業としてガバナンスやコンプライアンスを確保することは、「CSR活動」のベースとなる取り組みと言える。具体的には、各種ステークホルダーとの対話や監査役の選定、監査業務の適切な運営などが挙げられる。●人権
「人権」を守ることも、「CSR活動」における最重要課題の一つだ。会社として人権擁護の方針を明確化したり、従業員に人権擁護の意識を浸透させたりすることが大切となる。差別のない公正な雇用や従業員に対する人権教育などは、その一例だ。●労働慣行
従業員が働きやすい環境を整えることは、社会全体の労働改善につながる。それだけに、ワーク・ライフバランスの推進や長時間労働の是正、ハラスメントの撲滅、適切な職業訓練は、「CSR活動」として意義深い。●環境
環境問題への取り組みも「CSR活動」の一つだ。環境に悪い影響をもたらさない、あるいは環境保全や回復に取り組むといったことを心がけたい。省エネ、省資源、CO2削減なども活用の一例となる。●公正な事業慣行
「CSR」の観点からすると、自社だけが良ければという独占的な行動は許されない。あくまでも、社会に対して責任ある行動を取るべきだ。特に私的独占等や「下請けいじめ」などは、絶対に避けなければならない。公正な事業慣行に関する取り組み例としては、内部通報相談窓口の設置や従業員に対するコンプライアンス研修などが挙げられる。●消費者課題
自社の製品・サービスの欠陥により消費者に危害がもたらされたり、環境破壊等を招くことがないようにしたりすることも、「CSR活動」となる。そのためにも、エコ製品の製造や消費者とのコミュニケーションの強化を図りたい。●コミュニティへの参画
地域コミュニティへの貢献も、企業に期待される「CSR活動」だ。ボランティア活動や地域におけるスポーツの促進、地域住民を対象にした教育活動などの事例がある。「CSR活動」の企業事例
実際に国内企業がどのように「CSR活動」を行っているか、5社の事例を紹介していく。●ユニクロ
ユニクロは2006年から国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)とグローバルパートナーシップを結び、世界各地で難民支援活動を積極的に展開している。その活動は単に不要になった衣服を回収して難民に届けるだけでなく、難民の自立支援や職業訓練、雇用支援など多岐にわたる。衣料品メーカーとしての強みを活かしながら、国際的な社会課題の解決に貢献していると言える。ユニクロ:SOCIETY|服のチカラを
●富士フイルム
富士フイルムグループは、2030年度を目標とした長期CSR計画「Sustainable Value Plan 2030(SVP2030)」を策定し、計画的な社会貢献活動を推進。「環境」、「健康」、「働き方」、「生活」、「サプライチェーン」、「ガバナンス」の6分野を重点課題として設定し、長期的視点で改革に取り組んでいる。特に環境分野では、法令基準よりも厳しい独自の「リスク管理優先物質」を設定し、その代替物質の開発や使用量削減を積極的に進めるなど、先進的な取り組みを行っている。富士フイルム:CSR計画 SVP2030
●NTT
NTTは「人と社会のコミュニケーション」、「人と地球のコミュニケーション」、「安心・安全なコミュニケーション」、「チームNTTのコミュニケーション」という4つの大分類を設定し、それぞれに具体的な重点活動項目を定めている。特に環境保護分野に注力しており、「NTTグループGreen Innovation委員会」を設置して気候変動対策を推進。温室効果ガス排出削減への取り組みなど、通信企業としての特性を活かした環境負荷低減活動を展開している。NTT:NTTグループの取り組み
●ブリヂストン
ブリヂストンは「最高の品質で社会に貢献」という企業理念のもと、「環境」、「安心・安全なMobility社会」、「地域社会」、「AHL(Active and Healthy Lifestyle)とDE&I」、「人財育成・教育」の5分野を基盤とした社会貢献活動を展開している。具体的には、児童を対象とした自動車教室の開催や交通安全ルールを学べる教材の作成、地震などの被災地復興支援活動などを実施。タイヤメーカーとしての専門性を活かした安全教育と地域貢献を両立させている。ブリヂストン:社会貢献活動
●カバヤ食品
カバヤ食品は、社会的ニーズに応える健康食品の開発・販売を通じてCSR活動を実践している。注目すべきは2007年に発売した「ジューCグルコース」で、1型糖尿病の子どもを持つ母親からの相談をきっかけに開発された商品だ。糖分を安価においしく補給できる点が特徴で、発売後もNPO法人と協力して1型糖尿病患者支援活動を継続。2015年には「日本パートナーシップ大賞」でグランプリを獲得した。また、熱中症対策として塩分補給タブレットの開発や熱中症について学ぶ教材の提供も行っている。「CSR活動」に取り組むときの注意点・ポイント
最後に、企業として「CSR活動」に取り組む際の注意点を整理したい。●自社に適した活動を見極める
「CSR活動」といってもテーマは様々だ。それだけに、自社の強みや得意分野を活かすことが重要となる。自社の企業理念やビジョンを踏まえた「CSR活動」を設計することで、企業価値のアップと社会的責任の両立が実現できる。●コストとリターンを分析する
既に指摘した通り、「CSR活動」はコストが掛かる。どのようなコストが、どれだけ掛かるのかをしっかりと見極めた上で、自社が中長期的に得られるリターンとのバランスを考える必要がある。単なる慈善活動ではないので、自社利益と社会貢献をいかに両立させていくかという視点が求められる。●業務負担を配慮する
「CSR活動」だけでもそれなりの業務量となる。それだけに、できるならば専任部署を設置したいところだ。それが難しいのであれば、弁護士・公認会計士・税理士などの専門家に一部分を担当してもらうことを検討するのも有益だ。●中長期的な視野で取り組む
「CSR」は、短期的な成果を得にくい。何故なら、目指しているのが企業価値の創出だからだ。それだけに、中長期的な視野を持って取り組む必要がある。●ステークホルダーとの対話を重ねる
「CSR活動」はコストも掛かるし、中長期的な観点を持ってじっくり進めていく必要があるのは上述のとおりだ。それでも実施する意義があると企業が判断するのであれば、その根拠や自社の方針をステークホルダーとも共有する必要がある。彼らの理解・協力がなければ、実現は難しいと言わざるを得ない。●人権デューデリジェンスを意識する
人権デューデリジェンスとは、企業が自社やそのグループ会社の人権侵害に関するリスクを特定し、その防止や軽減に向けた施策を講じ、結果を検証した上で、適切に情報開示をしていくプロセスだ。外部の専門家とも連携し、人権デューデリジェンスを推進する必要がある。まとめ
「CSR」のメリット、デメリットを踏まえ、自社でも取り組むべきかどうかをぜひ検討してもらいたい。その上で、「推進していこう」と決断された企業のために、どんな手順でいけば良いかも軽く説明しておきたい。まずは、「CSR活動」の指針・方向性を策定することだ。参考にしてもらいたいのは、本文中でも紹介したISO26000で掲げられている「CSRの七つの原則と核心主題」。それと自社のビジネスモデルや事業の強みとを整合させていこう。次が、「CSR活動」を担う社内体制の整備だ。できれば、経営陣から取り組みの意義を全社に発信してもらってから、専任チームを立ち上げていきたい。実際に「CSR活動」がスタートしてからは、定期的に振り返りを行い、改善点に対して手を打っていこう。多くの企業が、「CSR活動」を通じて成果を得ることを期待したい。
●厚生労働省:CSR(企業の社会的責任)
【HRプロ関連記事】
●「MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)」とは? 意味や策定のメリット、企業事例、ポイントなどを解説
●「パーパス」とは?意味と必要性、パーパス経営の事例を紹介
●「企業理念」の意味や重要性とは? 経営理念との違いや企業事例も紹介
「CSR」に関する資料ダウンロード、セミナー、サービス、ニュースなどの最新コンテンツはこちら
よくある質問
●「CSR」の代表例は?
「CSR(企業の社会的責任)」の例には、環境保全活動や地域社会への支援、従業員の働きやすい環境づくりなどがある。例えば、ユニクロは不要な服のリサイクルや難民支援を行い、ブリヂストンは森林整備や水環境保全、タイヤリサイクルなどを展開している。- 1