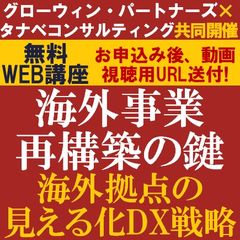「誰にでも使いやすい」を追求する可能性と「ユニバーサルデザイン」について
障がい者雇用に取り組んだ企業の感想として、(障がいの有無に関係なく)社員にとって「働きやすい職場」になったと言われることがよくあります。これは、障がい者の働きやすさを考えたことが、結果として他の社員にとっても使いやすくなったり、わかりやすくなったりするからです。障がい者雇用に取り組む企業では、このような視点を取り入れることによって、職場環境だけでなく、製品やサービスに関しても誰にでも使いやすいものにする工夫に繋げていることがあります。特にその考えが反映されているのが「ユニバーサルデザイン」です。ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、障がいの有無等に関係なく、誰もがアクセス・利用できる施設、用具、物品、情報伝達方法のことを指します。最近では、都市計画やまちづくりなどを進める時に、以前よく使われていた「バリアフリー」ではなく、「ユニバーサルデザイン」という概念が使われるようになってきました。
バリアフリーは、建築物や公共交通機関を利用して移動する高齢者や障がい者のために考えられたものでした。しかし、1980年代にノースカロライナ州立大学(米)で建築や物のデザインを研究していたロナルド・メイス教授が「障がい者など特別な人のための対応」とするバリアフリーの考えに違和感を持ち、“特別扱い”をせず気持ちの上でもバリアを生み出さないデザイン手法を研究したことが「ユニバーサルデザイン」が広がるきっかけとなりました。なお、教授ご自身にも障がいがありました。
「ユニバーサル」=「普遍的な、全体の」という意味があります。その言葉が示しているように、「ユニバーサルデザイン」とは「すべての人のためのデザイン」をいい、前述したとおり年齢や障がいの有無、体格、性別、国籍などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人にわかりやすく利用できるようなデザインです。このような考え方のもとに作られた製品やサービスは、実は私たちの身の回りにもたくさんあります。
例えば、お金は、視覚障がい者や視力が弱い人でも材質や形状で判別しやすいようにしてあります。五円玉や五十円玉には硬貨中央部に特有の穴があったり、硬貨の側面には細かく刻まれた溝があったりします。紙幣には右下と左下にホログラムや識別マークが印刷されており、そのインクなどの形状を触ることで金額が区別できるようになっています。また、ペットボトルや調味料の容器には、掴みやすいようにくぼみやクビレがあり、その工夫が開けやすさや注ぎやすさ、分別のしやすさに繋がっています。
センサー式の手洗い場や自動ドア、幅の広い改札など、公共設備にもユニバーサルデザインが施されています。自動販売機は、料金投入口を受け皿型の大きなものにしたり、商品選択ボタンを低い位置に取り付けたり、タッチパネル式の電光掲示板型にしたりすることで、背の低い子どもや車椅子利用者が使いやすく、また一番上の商品を買えるように考えられています。
障がいから生まれたアクセシビリティの向上
最近では、IT機器やWEBサービスにおいても「誰にでも使いやすい」という点が注目されており、高度な「アクセシビリティ」が標準機能されているツールも普及しつつあります。アクセシビリティとは、「利用しやすい」「便利である」と訳されることが多く、一般的には利用する人が円滑に利用できることを意味します。例えば、バリアフリー化が進んでいる街中でも、車椅子でスムーズに移動できるルートはまだ限られているのが現状です。このような状況に対応するために、地図や経路検索などのサイトでは、目的地までの最短ルートだけでなく、車椅子用の移動ルートや目的地の車椅子対応の状況が表示される機能がついています。
実は、この機能を活用しているのは、車椅子の人だけではありません。「ベビーカー」を活用している母親たちも利用しています。ベビーカーは誰もが活用する可能性があるにもかかわらず、「どのように移動するのが効率的なのか」「その店はベビーカーに対応しているのか」という情報が少ないようで、車椅子利用者用の機能が重用されているのです。このように誰かの使いやすさを追求することで、また別の誰かの使いやすさを生み出す可能性が大いにあります。
実際にITの技術のなかには、障がいの難しさや不便さから生まれたものが少なからずあります。例えば、視覚障がい者の対面コミュニケーションを支援するため、カメラでとらえた人の顔を解析し、その人の情報を音声などで伝える技術が開発されています。この技術が実用化されることにより、視覚障がい者がひとりで出掛けたときに、出会った人が誰かを認識することができます。また、目的地までのルートを音声で案内し、実際の状況をカメラなどで確認しながら、周囲にある物体の情報を音声で知ることができる技術もあります。
職場に聴覚障がい者がいるときには、手話通訳者の同伴や音声を文字に起こす必要がありますが、音声会話をリアルタイムでテキスト変換することができるようにもなりました。そのため耳が不自由な人でも周囲とコミュニケーションを取りやすくなりますし、会議などの会合にも参加しやすくなります。また、障がい者だけでなく、外国人がいる場合には、翻訳機能を合わせて活用することで、意思疎通が図りやすくなったり、今まで以上に心情を理解しやすくなったりしています。
ある自動車メーカーでは、聴覚障がい者の運転を支援する技術を開発しています。聴覚障がい者は、周囲の音を耳で聞いて判断するのが難しく、救急車などの緊急車両が近づいても気づかないことがあります。しかし、自動車に設置されたマイクでとらえた周囲の音を解析し、それをディスプレイにテキストで表示させたり、ハンドルを振動させてアラートを出したりするなど、聴覚以外の手段で運転手に知らせることができます。このような技術は聴覚障がい者だけでなく、耳が遠くなった高齢者にとっても実用的で、さらに健常者にとっても利便性につながります。
多様性から生まれるイノベーションや技術は、障がい者や高齢者はもちろんですが、他の人にとってもより使いやすい、より快適な生活をサポートしてくれるのです。
近年は、障がいを「社会モデル」という考え方から捉えるようになっています。これは、「障がい」そのものが問題なのではなく、「障がい」が主に社会によって作られていることを問題とする考え方です。そして、社会的障壁の多くは社会的環境によって作り出されたものと捉えます。以前は、障がいを個人の問題として、個別のサポートを必要とする「医学モデル」と呼ばれる考え方が一般的でした。しかし、世界保健機構(WHO)が国際生活機能分類(ICF)という考え方を採択し、障がいは個人の特性と環境の相互作用で決まるという考え方の分類に変わっています。
英語が話せない日本人が英語圏に行くと、さまざまな面で不便を感じることがあります。しかし、日本で暮らしている分には、言語の不自由を感じることはありません。近視の人は裸眼のままでは生活しにくいかもしれませんが、サポートしてくれる眼鏡やコンタクトレンズがあれば、やはり不自由を感じることはありません。環境因子と特性によっては障がいになってしまうことも、環境や視点が変われば障がいではなくなります。つまり、障がいという何らかの不便さや不自由さを多様性と捉えると、新たな技術の進歩やイノベーションにつながる可能性があるのです。
- 1