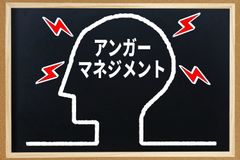感情をコントロールするときに大切なのは、認知(考え方、捉え方)を変えることである。
しかしながら、この「認知を変える」とはなかなか難しいものだ。
認知を変えることの難しさ
例えば、有名な「シロクマ実験」というものがある。これは、1987年にアメリカの心理学者であるウェグナー(Wegner,D.M.)によって行われたもので、概要は以下のようなものだ。(1)まず、実験参加者たちをA~Cの3つのグループに分ける。
(2)次に、各グループにシロクマの1日を追った映像を見せます。
(3)そして、それぞれのグループにそれぞれ違った依頼をする。
(4)Aグループには、「シロクマのことを覚えておいてください」とお願いする。
(5)Bグループには、「シロクマのことを考えても考えなくてもいいです」とお願いする。
(6)Cグループには、「シロクマのことだけは絶対に考えないでください」とお願いする。
(7)その後、参加者たちには一旦解散してもらい、ある一定期間をおいて再度集め、映像のことについて覚えているか尋ねる。
さて、A~Cのグループのうち、最もシロクマの映像のことを覚えていたのはどのグループだろうか。実は、「シロクマのことは絶対に考えないでください」とお願いされていたCのグループだったのだ。この実験結果から、認知をコントロールするのが、いかに難しいかが理解できるだろう。人は、考えるなと言われると考えてしまうものなのだ。
では、感情をコントロールするため認知を変えるには、どうすればいいのだろうか?認知行動療法では、いろいろなワークシートを用いて、認知の癖をなくしていくのだが、もっと手軽な方法もある。
認知の癖をなくし感情を抑える、手軽な方法とは?
認知の癖をなくす手軽な方法とは、いつもの認知が浮かんだ時に、とっさに「と思った」と付け加えることだ。例えば、
「自分はミスが多い」、「自分なんて価値がない」
と考えて落ち込んでしまう場合は、
「自分はミスが多い」と思った、「自分なんて価値がない」と思った、
と付け加える。
たったこれだけで、自分が落ち込むに至った理由・内容は、確実なものではなく、単なる自分の推測ということとなる。これにより、認知と距離を置いて、第三者目線で冷静になることができる。
これは不安な感情だけではなく、怒りの感情にも有効だ。
「あいつはなんて理不尽なんだろう。許せない」も
「あいつはなんて理不尽なんだろう。許せない」と思った
とすると、怒りもコントロールすることができる。
不安や怒りの感情をある程度コントロールできるようになれば、不要な争いが避けられて、仕事や日常生活で過ごしやすくなるはずだ。ぜひ試してみていただきたい。
koCoro健康経営株式会社 代表取締役
Office CPSR 臨床心理士・社会保険労務士事務所 代 表
一般社団法人 ウエルフルジャパン 理 事
産業能率大学兼任講師
植田 健太