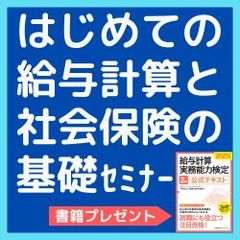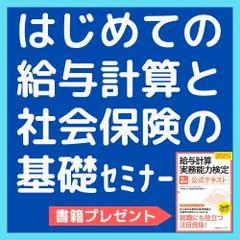解雇の金銭解決を考える上で、この内容を正確に理解する必要があるということを強調したいです。さらに、制度を導入することで、どのような問題点および良い点があるのかも踏まえ、今後「解雇の金銭解決」をどうすべきかを考えていただきたいと思います。
「解雇の金銭解決」に関するこれまでの議論と、“望ましい法制度の在り方”について
成蹊大学法学部 教授 原 昌登氏
「解雇」に関する基本的な法政策の歴史

はじめに、「解雇」に関する基本的な法政策の確認からです。歴史的な展開を見ると、まず民法では「解雇自由」の原則が掲げられています。これを労働法が修正するという構造です。また、労働基準法における規制は、戦前の工場法(改正工場法施行令)を拡充した「手続規制」が中心になっています。
次に、判例における「解雇権濫用法理」という考え方です。昭和20年代、解雇は実態として広く行われていました。しかしその後、高度経済成長期を迎え、社会システムの変化・成熟が進んでいく中で、長期雇用慣行を柱とする“日本的雇用システム”が定着・浸透していきました。昭和40年代から50年代に掛けて定着した「解雇権濫用法理」が、現在では労働契約法の中に条文として盛り込まれています。
これと並行して、「整理解雇法理」も形成されていきます。昭和40年代半ば以降の構造的な不況により、数多くの企業で雇用調整がなされました。大企業ができる限り解雇を回避しながら雇用調整を実施したことを裁判所がモデルとし、判例では具体的に4つの判断ポイント、いわゆる「整理解雇の4要件」を確立しました。それが、「人員削減の必要性」・「解雇の必要性」・「人選基準の合理性」・「手続の妥当性」です。
「金銭の支払いが解雇を有効にする」は大きな誤解
ここからは、「解雇の金銭解決」を巡る議論について見ていきます。解雇の金銭解決に関しては、非常によく誤解されることがあります。それは、「金銭の支払いによって解雇を有効とする」話だという誤解です。そうではありません。日本の法制度上は、「解雇が無効=労働契約の継続=職場への復帰」が原則となります。それ以外の解決策を制度的に可能にするという議論こそが、解雇の金銭解決なのです。実は元々、「労働者に金銭的な救済を認めるべきだ」という論点がなかったわけではありません。解雇の金銭解決に関する議論は、1990年代後半、主に経済学における「規制緩和」論を受けてスタートしています。この解雇の金銭解決に関して、近時には注目すべき研究業績が挙げられます。それが、山本陽大さんの『解雇の金銭解決制度に関する研究』です。以下、これを参考にさせていただきます。
議論の歴史的展開を見ると、まず、「解雇権濫用法理」の立法化が挙げられます。2001年に労働政策審議会(労政審)の分科会で審議が開始され、労働基準法の一部を改正するという流れで議論が進んでいきました。ところが、金銭解決についても立法化しようとする点に対して労政審で批判が続出。その結果、金銭解決の部分は改正案には盛り込まれませんでした。
では、この時の議論に対して学説はどう対応したのか。解雇ルールの立法化自体については、賛成の見解が多く見られました。ただし金銭解決に関しては、使用者側に申立ての権利を認めることに対する批判的な立場が多数ありました。
次は、「労働契約法」制定の際の議論の動きです。2004年に「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」が発足。翌年、報告書をまとめました。総論としては、「解雇の効力判断」と「金銭解決」の二本立てであり、「和解金は雇用関係解消の代償である」とされました。
金銭解決を労働者が申し立てられることは当然として、使用者からの申立てを認めるべきかが論点となりました。まず差別的解雇や労働者の正当な権利行使を理由とする解雇については、使用者からの金銭解決の申立てはできないとされました。これに対し、使用者側の責任ではないような事情であって、労働者の職場復帰が困難だと認められる特別な事情がある場合に限っては、使用者からの申立ても可能とされました。さらに、事前の集団的な労使合意を申立ての要件とすることや、使用者からの申立ての場合には最低金額を設けることなど、幅広く議論がなされました。
これに関する労使の反応として、労働者側は導入自体に反対のスタンスで、使用者側は制度の早急な導入を求めたものの、一部に関しては反対しました。
一方で学説の反応としては、「使用者の解雇にかかるコストの計算が容易になることで、使用者に対する労働者の従属性を高めるのではないか」という懸念が示されました。また実務上、「労働者の職場復帰が困難な事情があること」という条件は機能し得ないとの指摘もありました。
その後の経過としては、議論がどんどんトーンダウンしていきました。結局、審議は一時中断。その後再開されたものの、最終的には金銭解決の話抜きで労働契約法が成立しました。
三つ目の大きな出来事が、「アベノミクス下での動き」です。これについては、複数の会議体が置かれた点が特徴的でした。そのうちの一つが「規制改革会議」です。こちらは、「解雇無効時の救済手段の多様化」というアプローチでした。もう一つが、「産業競争力会議」。こちらは、「諸外国並みの紛争解決システムの整備」というアプローチでした。この背景には、「海外企業からの投資を呼び込む」という視点があったのです。
この二つの会議に対する学説の反応としては、「金銭解決の申立権を使用者側に認めること」を批判する見解が多くありました。その一方、「使用者側にも金銭解決の申立てを認めるべき」とする見解もありました。また、既に労働審判制度等が存在することを指摘し、金銭解決制度の創設に否定的な見解も見られました。
他方で、現実に金銭解決が行われている事実こそ、金銭解決の制度化の妥当性を根拠付けるという見解や、実態として低額で金銭解決がなされている、特にあっせん(斡旋)のようなシステムにおいても援用できるという点で、「制度化に相当程度のメリットがある」と指摘する見解もありました。