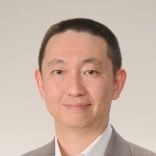くだかざらんや武士(もののふ)の
国安かれと思い切る太刀
桜田門外の変という、いわばテロの実行犯である薩摩藩士・有村次左衛門の辞世の句である。
末弟・有村次左衛門
桜田門外の変が、その後の日本にどのような影響を与えたかは、多くの方がご存知であろうと思うし、その是々非々は私には分からない。今回は、桜田門外の変そのものではなく、水戸脱藩浪士が中心となる政治的一大事件の中で、薩摩藩唯一の参加者であった有村次左衛門という若者の行動理論を考えてみたい。
有村の家は生粋の薩摩武士である。ただ微禄であった。
有村俊斎(後の海江田信義)、有村雄助という二人の兄を持つ彼は、どちらかと言えば学問や弁舌に長けたタイプではなかったようである。薬丸自顕流を学び、後に江戸で北辰一刀流を修め、武の道を究める以外、進む道はなかった。
ちなみに長兄・俊斎は一八六二年八月の生麦事件で英国人リチャードソンにとどめを刺した人物であり、戊辰戦争では、総督参謀まで務めた人物である。
長兄と比べると、次左衛門はあまりにも知名度が低い。だが、その人物を直接知る人々からは、「有村兄弟は下に行くほど魅力的になる」ともいわれている。
決断の刻(とき)
学のない次左衛門は、江戸出仕中に安政の大獄を知る。政治的なことは何ひとつ分からないながらも、次兄雄介からの影響も手伝って、「井伊直弼切るべし」という想いを強めていく。薩摩藩は当初、水戸藩に呼応して藩を挙げて井伊暗殺を企てていたものの、藩内統制が困難を極め、藩としての参加を断念せざるを得なくなった。
そんな中、雄介と次左衛門は薩摩藩士の面目を守るため、二人だけで加わることを決意する。
しかし、次左衛門より多少学のあった次男雄介は、藩の情勢と水戸藩への義理とのはざまで揺れる。藩内の政治的な動きを考えれば、変を起こすのは得策ではない。また藩命は「戻れ」である。がしかし、これまでよくしてくれた水戸藩士の面々や日下部家を裏切ることもできない。何よりも、「井伊切るべし」
しかし揺れに揺れた揚げ句、次男雄介も結局井伊暗殺を断念する。
武で生きる以外、道がない次左衛門の思考はいたって単純であった。
「井伊は悪である。故に悪を放置しては国が滅びる。井伊を倒すのみ」の一点であった。もちろんそれが正しいかどうかは分からない。しかし次左衛門の中ではゆるぎない信念であった。
さらにその奥には、次左衛門の自分自身に対する行動理論が深く横たわっていた。それは、「自分は剣以外何もできない人間である(観)故に剣によって道を開かなければ(因)己の存在は無意味なものになる(果)剣を活かせ(心得モデル)」というものであろう。
彼は自分と比較して、学もあり知名度も高く藩上層部とのパイプもある兄と比較し、自分自身が生きる道を剣と定めた。先天的な性格がのんびりとして冒頓としていたことも幸いし、劣等感を感じることはなかったようであるが、それでも兄たちとの違いを理解し、自分の存在意義が感じられる場を剣に求めたのである。
命の使いどころ
次左衛門はようやく機会を得た。手前勝手な弾圧(少なくとも次左衛門にはそう見えていた)で幕政をあやつる井伊の暗殺は、彼の生きる意味を実現するにおいて、どうしても必要な舞台であった。
一八六〇年三月三日、その日の天気は雪であった。
一発の銃声で始まった大老暗殺は、直弼を駕籠から引きずり出し、その首を斬ることで幕を閉じるはずであった。
そして事実次左衛門は井伊を倒した。
が、倒れていたはずの彦根藩士の一太刀により次左衛門自身も致命傷といえる傷を負う。
数町歩くもかなわず、死を悟った次左衛門は、命を落とす。
しかし、彼は己の道である剣をもって自身の存在意義を示すことができたのである。
母親・れんから言われていた「皇国のために尽くしなさい」という教えを忠実に遂行し、命を使い切ったのである。
次左衛門の死生観
桜田門外の変が起こる二年前の一八五八年、薩摩藩主島津斉彬が急死した。当時三兄弟は江戸にいたが、長兄俊斎は「薩摩に帰る」ことを主張した。
「薩摩に帰る」が意味するところは、「殉死」である。しかし次左衛門は「残ります」と明言した。
「殉死とは無駄死にの事である。命は事を成すために使うべきものである(観)。故に、事を成すために失われたならば(因)その死は意味あるものになる(果)が、事を成さずして失ったならば(因)、その死は意味をなさない(果)。ことを成せ(心得モデル)」という次左衛門が持つ行動理論から長兄を説得したが聞き入れられなかった。
次左衛門にとって、命とは長らえるものではなく、使うものである。
それ故に、ひとたび使い道を見つければ、命は惜しむ対象ではなくなる。ひたすらに使い続け、目的を達成するまで留まることをしない。それ以外の全ては無用なことであり、兄たちが成す議論・政治的交渉など、次左衛門にとってさまつなことであった。
使命とは、その字が成す通り「命を使うべき対象」を指す。使命が明確になった時、命はまさに「使うもの」となり、それが人間を突き動かすのである。
自らの使命とは何なのか。明確に見つけられている人は次左衛門のように迷わないのであろう。
- 1