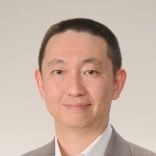「幕府しか見ず、日本の未来を見なかった保守派」というイメージで描かれることが多い彼は本当にそのような人物だったのか?
今回は、彼の行動理論を探ってみたい。
井伊直弼は1815年10月、彦根城の一角にある槻(けやき)御殿で生まれた。
兄のいた直弼は、藩主を継ぐことはなく、通常ならば養子となって家を出ていく立場であった。
しかしなぜか養子縁組の話が中々成立しなかった直弼は藩から三百俵の扶持を支給され質素な屋敷で暮らすことになる。
「世の中をよそに見つつもうもれ木の 埋もれておらむ心なき身は」と詠い、この屋敷を「埋木舎」と呼んだ。ここで自分の人生が朽ちていくことはやむを得ないが、己の心だけは決して埋もれないという想いの表明であった。
事実兵学、和歌、陶芸、禅、居合や華道、政治、海外事情などあらゆることに精力的に取り組んだ。
身に着けた文武が決して表に現れることはないと思いつつも彼は、一瞬一瞬に全力を注いだのである。
直弼の転機
1846年直弼の道に大きな転期が訪れる。兄の病死により1850年には13代藩主、1858年43歳で大老に就くことになるのである。埋木舎で埋もれていくはずであった彼の人生は、ここから日本という国の進路を定める表舞台に出ていくことになる。
直弼の埋木舎での人生は15年に及んだが、この15年は埋もれていたのではなく、その後にやってくる舞台のために己を磨き続けた大切な一瞬の積み重ねであった。
直弼の中には、「人生とは積み重ねである(観)。一瞬一瞬に全精力を傾けることこそが(因)自分の人生を築き上げる(果)。故に一瞬を粗末にするな(心得モデル)」という行動理論が創りあげられていったのであろう。
彼は13歳のころから禅の修行を行っていた。
「人生にはたくさんの風が渦巻いている。うまくいった時、失敗した時、認められた時、否定された時など、どのような風が吹こうとも天に輝く月のように、清々と生きよう。(八風吹不動天辺月)」
「己の心がけ次第で、あらゆる場所が自分を高める道場になる(歩々是道場)」
「どのような日でも毎日は新鮮で自分の人生にとって最良の日である。雨の日も風の日も、その時の感情や状態を大いに味わって過ごせば、かけがえのない一日になる。(日々是好日)」
など、彼の行動理論を創りあげる教養が禅の修行において積み上げられていった。
居合も同様であろう。宗派それぞれによりさまざまな教えはあろうが、居合には「一瞬の中にこそ真実がある」という思想が流れている。
そうした積み重ねから、彦根藩藩主、幕府大老という役目を果たす時を迎えるのである。
井伊家は江戸幕府が開かれたころから将軍を近くで守るのがお役目であった。当然井伊家に脈々と伝承される行動理論として「当家は幕府を守るための家であり(観)幕府は国を守る唯一の機関である(観)。故に、己の全力を幕府のために使え(心得モデル)。なぜならば幕府を守ってこそ(因)この国が守られるからである(果)」というものが、同時に直弼に中にもあったことは推察できる。
日本の転機
そしてついに、日本そのものに転機が訪れる。1853年4艘の黒船が浦賀沖に姿をあらわすのである。アメリカが日本に迫った開国は様々な風を起こした。
鎖国か開国か、日本が二分三分する中、直弼は、「幕府主導による開国こそが日本をさらに強くする」と考えていた。(諸説あり)
京の朝廷では孝明天皇が開国に否定的であり、国の考えは一つにはまとまらない状態が長く続いていたが、大老となった直弼は己の意見を静かにしかし真っ向から周囲の人間に説いていた。
そして1858年日米修好通商条約を結び、自由な貿易の条件が整うのである。
が、当然反対派も多く、水戸藩主徳川斉昭は条約締結に反対し、京の公家を通して直弼排斥の密勅を天皇から出させることに成功する。
しかし斉昭のこの行為は定めに反するものであり、直弼は当然これに対して大老としての役目を果たさざるをえない。これが安政の大獄である。
直弼は「幕府の主導で開国する事こそが国のためであり、条約締結はそのための正しい道である。この道を妨げることは、国の発展を阻害する行為であり、幕府を守るべき自分が道を整えなければならない」と考えていた。
これらの処分は苛烈なものであり、当然水戸藩側としては、抗う算段を整える必要があった。この算段こそが、桜田門外の変である。桜田門外の変そのものについては、前回も触れているので割愛するが、変が起こる寸前に直弼は
近江の海 磯うつ浪の いく度か 御世に心を くだきぬるかな(近江の海で磯に何度も打ちつける波のように、私も世の中のために心を尽くしてきたなあ)という歌を詠む。
この歌は己の役目を終え死を覚悟したものであるように見える。
そして1860年、桃の節句の式典に出席するため駕籠の人となった直弼は桜田門外の変で、その役目を終えるのである。
余談ながら彼が残した茶の湯の精神に、一期一会に連なる「独座観念」というものがある。
「主人も客も、会が終わっても、互いへの心は残すものである。主人は客が見えなくなるまで見送り、席に戻ってこの一期一会の瞬間に感謝しながら一人で茶をたてる」
これこそが一期一会を単なる刹那主義と一線を画す精神とするのである。事を成した彼は籠の中で「独座観念」していたのであろう。
- 1