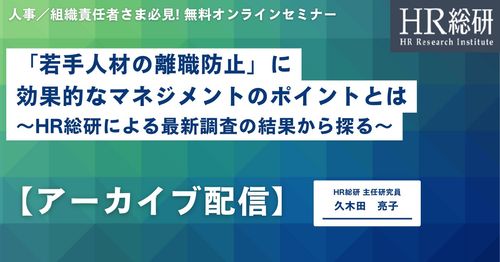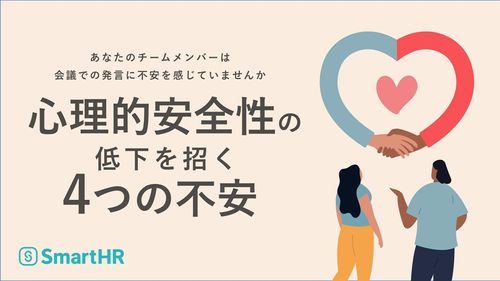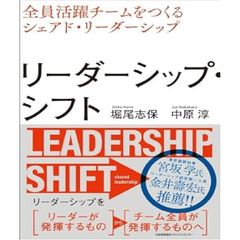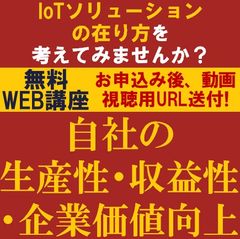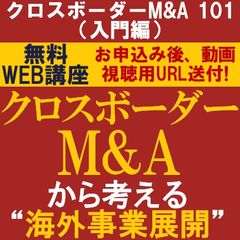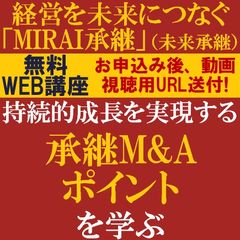「イノベーション」の意味と定義
「イノベーション」とは、モノや仕組み、サービス、組織、ビジネスモデルなどに新たな考え方や技術を取り入れて新たな価値を生み出し、社会にインパクトのある革新や刷新、変革をもたらすことを意味する。現在の企業にとって、イノベーションを成功させられる組織であるかどうかは非常に重要な経営課題だ。ところが、「イノベーション」という言葉の意味を考えた時、「何か新しいことに挑戦すること」、「停滞した状態から変革をおこすこと」といったような、なんとなく、ぼんやりとしたイメージで使用していないだろうか。まずは正しい概念を理解するために、大前提として、「イノベーション」の言葉の意味と定義から確認していこう。
●そもそもビジネスにおける「イノベーション」とは
現在企業が経営において必要としている「イノベーション」とは何かというと、「これまでにないサービスや、今はまだ存在していない新たな製品などを生み出すこと」である。語源の「innovare」(ラテン語)がもつ「新しくする、更新する」といった意味から派生した。よく「技術革新」と和訳されてきたが、本来は技術に限定する狭義の単語ではない。サービスや組織、ビジネスモデルなどの新たな考え方や新技術によって、今までにない、まったく新しい価値創造を目指すことだ。単に新しい物を作る「クリエイト(クリエイティブ)」とは異なり、「社会に対して革新・刷新・変革をもたらす」という広い概念である。
●「リノベーション」との違い
「リノベーション」(renovation)とは、日本語で「更新」、「刷新」、「改修」などと訳される。それに対し、「イノベーション」(innovation)は日本語で「革新」、「改革」、「改変」などと訳される。一見、似ているが、両者には明確な違いがある。リノベーションは既存のものに対して修復、改善を加えて、新たな用途や機能、価値を加えるのに対し、イノベーションは、それまで無かった、まったく新しいものを生み出す意味がある。「イノベーション」の種類
近年、ビジネスシーンで頻繁に目にするようになった「イノベーション」という概念は、ヨーゼフ・シュンペーター、クレイトン・クリステンセン、ヘンリー・チェスブロウの3人の提唱者による理論から発生した。それぞれの理論は下記の通りだ。(1)ヨーゼフ・シュンペーターの「5種類のイノベーション」
ヨーゼフ・シュンペーターはオーストリアの経済学者で、1912年に発表した著書の中で「イノベーションを核とした経済発展理論」を展開した。彼は「経済の発展には企業家よるイノベーションが重要である」と提唱。下記の5種類をイノベーションとして挙げている。・プロダクト・イノベーション(新しい生産物の創出)
従来とはまったく違う、革新的な新商品(新製品・新サービス)を開発すること。
・プロセス・イノベーション(新しい生産方法の導入)
企業の商品(製品やサービス)を大きく変化させるのではなく、生産工程や流通方法を改善すること。
・マーケット・イノベーション(新しい販売先・消費者の開拓)
新たな市場に参入し、新たな顧客、ニーズを開拓すること。
・サプライチェーン・イノベーション(新しい供給源の獲得)
商品をつくるための材料や、その原材料の供給ルートを新規開拓・確保すること。
・オーガニゼーション・イノベーション(新しい組織の実現)
組織変革によって業界や企業に大きな影響を与えること。
(2)クレイトン・クリステンセンの「創造的イノベーション/破壊的イノベーション」
ハーバードビジネススクール 教授のクレイトン・クリステンセンが、著書の中で提唱した理論。イノベーションには「創造的/破壊的」の2種類の手法があるという。・創造的イノベーション
顧客の意見や要望を取り入れながら進めるイノベーション。「持続型イノベーション」ともいう。
・破壊的イノベーション
既存の概念にとらわれず、新たな発想を積極的に取り入れることで、新製品や新サービスを生み出していくイノベーション。「破壊型」ともいう。
・イノベーションのジレンマ
クレイトンは上記の理論とともに「イノベーションのジレンマ」という課題も説いている。「イノベーションのジレンマ」とは、イノベーションに取り組む過程で起こった何かの要因によってイノベーションが起こせない状況に陥り、その結果、他の追随や追い越しを許してしまうことである。
(3)ヘンリー・チェスブロウの「クローズドイノベーション/オープンイノベーション」
ハーバード大学 経営大学院 教授のヘンリー・チェスブロウが提唱した、イノベーションの2つのパターン(クローズド/オープン)である。・クローズドイノベーション
1990年代以前の、研究から製品開発までを自社の経営資源のみで行う「自前主義」が主流だった時代に流行したイノベーションを指す。
・オープンイノベーション
外部資源や他業種がもつ技術・ノウハウを組み合わせて活用する手法。90年代以降、インターネットやテクノロジーの飛躍的発展に呼応してグローバル化・産業構造の変化・人材流動化が加速し、市場競争も激化したことで、大企業といえども自社の資源のみでイノベーションを起こすことはほぼ不可能となったために注目された。現在の日本では、クローズドイノベーションからオープンイノベーションに変化しているといえる。
なぜ、今「イノベーション」が注目されているのか
言葉の来歴や概念・定義を抑えたところで、次に、なぜ現在、「イノベーション」に注目が集まるようになったのか、その理由や背景などを確認していこう。主な理由は下記の4つである。●大きな経済成長
「イノベーション」に成功した企業は、莫大な経済的成果を得る傾向が大きい。そのため、企業が成長を促進し、維持していくために、新たな価値創造するイノベーションを求めることは当然だ。つまり、イノベーションを成功させ、新たな市場開拓ができれば、収益拡大と維持につながるのだ。●企業課題の解決と生産性向上
日本に限らず、「人手不足」は企業の大きな課題となっている。人手不足の結果、長時間労働や健康経営の阻害など、社員と企業どちらにとっても良い影響は生まれない。例えば技術面でのイノベーションによって新たな生産方式を確立することで、社員の生産性向上や労働課題の解決を目指している企業は大変多い。●企業規模にかかわらない市場独占の可能性
イノベーションによって生まれた新たな商品(製品やサービス)によって、新しい価値創出、市場開拓を可能にする。イノベーションを起こせば、競合他社がまだ参入していない市場を一時期であっても独占することが可能になる。この「市場独占」の可能性は、資本力の小さい中小企業や個人事業にも等しくあり、大企業に対抗しうる機会にもなるだろう。既存の市場では競争できなかった小規模な企業にとっても、イノベーションの成功は魅力的な取り組みなのである。●国内外での市場競争の優位性獲得
企業にとって、市場競争における「優位性獲得」は、戦略的事業の肝ともいえるだろう。例えば、新技術の特許を取得することは企業の大きな強みになり、顧客に新たな価値を提供することにもつなげられる。さらに、既存顧客に対するメリット提供だけでなく、新規顧客獲得にも重要な要因となる。もちろんこれは国内に限らず国外に対しても有効で、グローバルな優位性獲得も視野に入れられるだろう。日本における「イノベーション」創出の現状
戦後の日本は、新幹線やインスタントラーメン、トヨタ生産方式など、世界を席巻するさまざまな発明を続け、今でも人々の生活を支える製品やサービスを生み出してきた。ところが、現在はその余地が少なくなり、新たなイノベーションの創出に苦しんでいる。NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)とJOIC(オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会)が発表した『オープンイノベーション白書 第三版』によれば、オープンイノベーションに対する実施率や予算、従事者が欧米企業と比べて低い水準となっている。もっとも、『オープンイノベーション白書 第三版』では、日本には高い研究開発能力があるとされ、世界でもトップレベルの研究開発費と研究者数を誇り、論文数や有力な特許の数も世界において高い水準であるとも示されている。さらに2021年3月に政府により「第6期 科学技術・イノベーション基本計画」が策定され、「イノベーション力の強化」、「研究力の強化」、「教育・人材育成」を3本柱とし、5年間で約30兆円の研究開発投資を目指すと発表された。
WIPO(世界知的所有権機関)が発表しているグローバルイノベーションインデックスのランキングで日本は、2011年からトップ10圏外が続くが、2012年の25位から2023年は13位まで順位を上げている。つまり日本における「イノベーション」創出の現状は発展途上と言える。
「イノベーション」を起こすための3つの企業課題
グローバル化が進み、新興企業の台頭や技術革新など、これまで日本企業が保っていた「競争優位性」が失われつつあるといわれて久しい。近年、新たな市場開拓を成功させたイノベーション事例は確かに少ないのが実情だ。日本が誇る技術力はいまだに高い評価を得ているというのにイノベーションが生まれないのは、日本企業に独特の課題があるからではないかといわれている。それでは、日本企業がイノベーションを起こし、成果を上げるための「課題」とはどのようなものだろうか。●継続可能なイノベーション維持ができていない
技術革新や市場環境の急速な変化に対応するためには、「一度イノベーションを起こせたらもう安泰だ」という思考ではいけない。企業の成長維持のためには、「継続的なイノベーション」と「新規顧客と市場の開拓」を常に続けていく必要がある。日本企業は、既存の製品・サービスを高機能化させる方向での持続的イノベーションをやめられない傾向が強いが、既存商品のグレードアップでは、日々新たなものが生み出される現状には対応できず、だんだんと競争力が下がってしまうのだ。これも、日本企業が抱えるイノベーションに対する課題のひとつである。自社商品がもついわば「寿命」をきちんと認識し、適切なイノベーションを実施することが必要だ。●「イノベーション・マネジメント」導入が遅れている
イノベーションに関する企業の意思決定は、何よりも「スピード」が大切だ。アイディアやビジネスモデルの創造、そして事業化するまでのプロセスを迅速にしなければならない。つまり、既存事業を持続させようという考えでは、イノベーションが起こりにくいのだ。そこで、イノベーションをいち早く起こすことに特化した「イノベーション・マネジメント」の迅速な導入、労働環境を変化させることが重要になる。●社内制約と企業ローカル文化による消極的な姿勢
「成果主義」を標榜する企業が増えつつあるが、日本企業にはまだまだ旧態依然とした前提による人事評価制度が習慣として残っているといえる。失敗を恐れて、積極的なチャレンジよりも会社方針に従順にすごすことも旨とする社員も増えているようだ。また、コロナ禍で顕在化したように、規模の大小にかかわらず、社会情勢や市場の変化によってたやすく経営悪化に陥るので、「寄らば大樹の陰」という気持ちは強まり、必要な衝突であっても避けてしまう傾向がある。イノベーションの阻害要因として、これらの閉鎖的な企業ローカル文化や足並みをそろえたがる社員のマインド、企業制約が指摘されている。「イノベーション」を起こせる企業の特徴とは
積極的に市場開拓に臨み、閉鎖的なローカルルールを排除できる企業が「イノベーションを起こせる企業」だとわかった。それでは、実際にイノベーションに成功している企業に共通する「特徴」をあげてみよう。●市場変化と時代の流れに対し、常に敏感なアンテナを張っている
誰も思いつかないようなアイディアや、卓抜した経営センスによる閃きだけがイノベーションを生むと思われがちだ。しかし、前述の通り、イノベーションには、自社が長く培ってきた技術を向上させることで起こる「創造的(持続型)イノベーション」や、他社や外部との提携によってまったく新しい価値を創造する「オープンイノベーション」などもある。そして、「破壊的イノベーション」を起こすことができれば、短期間であったとしても、市場独占によって大きな利益を上げる可能性もある。市場の変化や潮流に敏感であること、常に模索を続けることが非常に大切だ。●リスクに対する正確な理解があり、適切なアクションがとれる
イノベーションは、「不確実性」と「リスク」が常に隣り合わせだといえる。特に「リスク」は企業の既存事業にも大きな影響を与える可能性があり、企業経営者は判断に慎重になる。しかし、経営陣や管理職がリスクに関して大きな誤解をしている場合がある。イノベーションを起こすには経営資源の先行投資は不可欠だ。財務状況を分析し、不確実性やリスクが高い場合は「何もしない」という選択肢を選びがちだ。しかし、これでは市場にイノベーションが起きた際には他社に出遅れ、売上・利益は獲得できない。さらには、既存事業からも撤退せざるを得なくなるかもしれない。経営層による「リスクの正確な理解」と、「適切なアクション」は、企業がイノベーションを起こす第一歩だ。●社内外でのコミュニケーション環境が整っている
「イノベーションを起こしやすい労働環境」というものがある。そのような環境構築のためには、企業側がイノベーション人材をきちんと支援する体制をとることが非常に大切だ。特に、「コミュニケーション環境」を整備することが最も重要な必要条件となる。潜在的な顧客ニーズを検知し、実現するための技術革新ができた時、イノベーションが生まれるという。そのため、イノベーションを担う人材には、積極的に顧客と会話する自由や、テストマーケティングが行なえるような「コミュニケーション環境」が必要だ。また、社外とのコミュニケーションだけでなく、社内でも他事業部間でコミュニケーションを活発に行わせることも、イノベーションを成功させる道である。「イノベーション」成功の企業事例
●P&Gジャパン
1973年の創業から50年以上になるP&Gジャパンは、これまでの歩みを「日本の暮らしとともに革新を続けた50年」と称している。育児事情を変えた紙おむつ「パンパース」や、スプレー型の消臭リフレッシャー「ファブリーズ」など革新的な製品を生み出した。特に2014年に誕生した、粉末でも液体でもなく、同社の独自開発による新素材フィルムで包まれた洗剤「ジェルボール」は指でつまんで洗濯機に投げ込むだけの画期的な商品で、計量不要の“ワンショットタイプ洗剤”という新たなジャンルの先駆者となった。●キリンビバレッジ
キリンビバレッジは、清涼飲料の製造・販売だけでなく、実は法人向けに健康経営を支援する「KIRIN naturals」というサービスも提供している。「KIRIN naturals」とは、健康支援商品の販売だけでなく、従業員の健康を維持するための施策立案から効果検証まで、健康経営を総合的に支援するサービスだ。具体的には動画配信サービス、eラーニングやセミナー、サーベイ、コンサルティングまで幅広い。同社の本業である清涼飲料に関するリサーチ力やデータ分析ノウハウが活用された新たなビジネスモデルと言える。●マクアケ
マクアケは、オンラインマーケットプレイス「Makuake」を運営している。この「Makuake」は、新しいモノを提供する事業者と、作り手や担い手に共感し、それを応援するサポーター(購入者)をつなぐ「応援購入サービス」が特徴。商品を作ってから販売するのではなく、作る前に販売する逆転的な商流により、新しいモノが次々に生まれる仕組み「0次流通産業」を創出した。2021年からは海外展開支援のためのプログラムも開始し、グローバルに広がる新しい商流を日本初で生み出している。また同サービスは、サービス産業生産性協議会(SPRING)が主催する日本サービス大賞の経済産業大臣賞を受賞した。まとめ
今後の予測が困難な時代となり、企業のこれからの存続、継続的な成長に「イノベーション」は欠かせない。一見すると理解していると思いがちな言葉の意味や定義、実際に企業が取り組むうえで大切な姿勢と解決すべき課題を本記事では取り上げた。重要なのは、ある企業に成功をもたらしたイノベーションが自社にも通用するとは限らないということだ。多様な定義から自社に必要なものを見つけ、解決すべき課題にフィットする「イノベーション」を創造することが肝要である。よくある質問
●「イノベーション」の言い換えは?
「イノベーション」(innovation)は日本語で「革新」、「改革」、「改変」などと訳される。言い換えの例としては、以下があがる。・革新
・改革
・改変
・一新
・刷新
●ビジネスにおける「イノベーション」とは?
ビジネスにおける「イノベーション」とは、「これまでにないサービスや、今はまだ存在していない新たな製品などを生み出すこと」。技術に限定する狭義の単語ではなく、サービスや組織、ビジネスモデルなどの新たな考え方や新技術によって、今までにない、まったく新しい価値創造を目指すことだ。単に新しい物を作る「クリエイト(クリエイティブ)」とは異なり、「社会に対して革新・刷新・変革をもたらす」という広い概念である。●「イノベーション」を起こすには?
「イノベーション」を起こすには、「継続可能なイノベーション維持ができていない」、「「イノベーション・マネジメント」導入が遅れている」、「社内制約と企業ローカル文化による消極的な姿勢」といった企業課題を解決することが必要。また、「イノベーション」を起こせる企業は、「市場変化と時代の流れ対し、常に敏感なアンテナを張っている」、「リスクに対する正確な理解があり、適切なアクションがとれる」、「社内外でのコミュニケーション環境が整っている」などの特徴がある。- 1