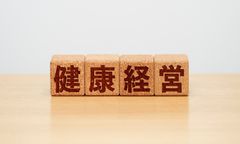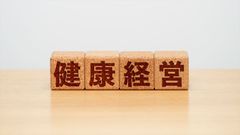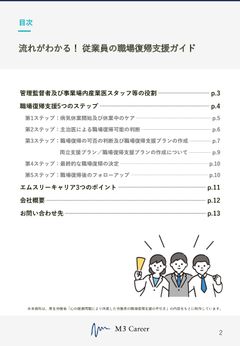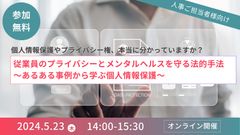「アンガーマネジメント」とは
「アンガーマネジメント」とは、怒りの感情が生じても上手に付き合い、コントロールしながら、適切に問題解決を図るスキルを指す。怒りは衝動的な言動や威圧的な態度をもたらす要因となりえるだけに、それを抑制し、適切なコミュニケーションにつなげていくことが重要だ。もちろん、すべての怒りが良くないということではない。怒るべき部分に怒り、怒る必要のない部分には怒らないと区別をすることが重要である。この考え方は、米国では1970年代から心理教育や心理学の分野で取り上げられていたが、近年は日本でも、職場環境の改善や業務パフォーマンス向上などを目的として、注目されるようになってきている。怒りの感情が高まると、周囲の人に八つ当たりをしたり、モノを壊したりしてしまい、どうしても職場の雰囲気や人間関係をも乱しがちだ。そうならないためにも、「アンガーマネジメント」に関する正しい理解を促していくことは企業にとっても意味があると言っていいだろう。
●怒りの仕組み
そもそも、人はどうして怒るのか。怒るという感情の仕組みがどうなっているのか。この点を考察してみよう。「アンガーマネジメント」では、第一次感情と第二次感情に大別される。第一次感情とは、心の中に蓄積されるネガティブな側面の感情を指す。具体的には、恐怖、不安、疲れた、悲しい、淋しい、ストレスがあるなどだ。それらが処理・表現しきれずに、許容範囲を超えてあふれ出てしまう時に現れるのが怒り(第二次感情)だ。すなわち、第一次感情がなければ第二次感情も発生しないということになる。
実は、怒りのなかでも注意しておきたい怒りもある。以下の4つが該当する。“持続的な怒り”、“歯止めが利かない怒り”、“頻繁に出る怒り”、“相手やモノを攻撃する怒り”である。いずれのケースも「アンガーマネジメント」で対処することを心がけたい。
●「アンガーマネジメント」は効果がない?
怒りをコントロールするには、正しい理解が必要だ。「アンカーマネジメントには効果がない」と感じた時、目的や手段が間違っているケースが大半である。そもそもアンガーマネジメントは、怒りの感情をなくすことが目的ではない。怒る必要のある時に適切に怒りを表現し、怒りが不要な時に怒りに振り回されないようにするためのノウハウなのである。またアンガーマネジメントの方法は様々で、人によって合う・合わないがあり、自分に適した手法を取り入れると、より大きな効果を期待できる。「アンガーマネジメント」の必要性
怒りの感情を爆発させてしまったことで、人間関係が破たんしたというケースはどこででもあり得る話だ。「なぜ、冷静になれなかったのか」と後で悔やむことになる。その怒りをコントロールできるか、できないかで職場環境や生産性も大きく変わってくる。「アンガーマネジメント」の必要性について説明していく。●「アンガーマネジメント」が注目された背景
近年、働き方やライフスタイルの多様化を背景に、従業員個々の価値観をお互い認め合おうという流れができている。とはいえ、自分が信じた価値観を社内や同僚に押し通そうとすれば、衝突は避けられない。その影響で怒りを溜め込む人も少なくない。また、社会全体でパワハラやセクハラなどのハラスメント対策に力を入れ始めている。部下を叱った際に、その気はなくてもパワハラと見なされてしまう恐れもある。そうした価値観の多様化やハラスメント防止に適応するために「アンガーマネジメント」が注目を集めている。
●「アンガーマネジメント」が必要な社員の特徴
「アンガーマネジメント」が必要となる社員には、いくつかの共通した特徴が見られる。例えば、日頃からささいなことですぐに怒ったり、怒りの持続時間が長かったりする社員だ。また、自らはあまり主張せず、ストレスを溜めがちな社員も危うい。いつか爆発してしまう可能性がある。さらには、リーダーや管理職層にも「アンガーマネジメント」は必須となってくる。パワハラへの理解、メンバーのマネジメントにとって有効であるからだ。いずれも、セルフコントロールの一環として、「アンガーマネジメント」を身につけることをお勧めしたい。「アンガーマネジメント」のメリット・効果
ここでは、「アンガーマネジメント」のメリットと効果について述べたい。●ストレスが緩和する
怒りを感じると、イライラさせられたり、それによって後悔したりすることがある。「アンガーマネジメント」を身につけると、そのようなストレスを緩和することができ、心の健康を保ちやすくなる。●スムーズなコミュニケーションが図れる
不適切な怒りに支配されると、本当に相手に伝えたかった気持ちや実現したかった想いが伝わりにくくなる。むしろ、誤解を招いてしまうこともあるくらいだ。「アンガーマネジメント」を実践することによって、言葉で適切にコミュニケーションが図れるようになるだろう。●柔軟性や視野の広さが身につく
価値観や考え方は一人ひとりで異なるものだ。「アンガーマネジメント」を通じて、その違いを受け入れられるようになると、自分自身の視野が広がり、人間関係も柔軟に築くことができるようになってくる。●マネジメントに活用できる
「アンガーマネジメント」は、自分自身だけでなく関わる人すべてが怒りとどう向き合っていくべきかを教えてくれる。それだけに、部下・メンバーに対する教育や指導としても役立つ。マネージャーには必須となるスキルと言えそうだ。●生産性が向上する
怒りの感情をコントロールできていないと、自分自身が仕事に集中できないだけでなく、職場環境や人間関係を悪くしてしまう。「アンガーマネジメント」を身につけることで、コミュニケーションが活性化され、仕事の生産性を上げていくことができるだろう。あなたはどのタイプ? アンガーマネジメント診断
怒りのタイプもさまざまある。ここでは、6つ取り上げてみたい。いずれも、日本アンガーマネジメント協会が公表する「アンガーマネジメント診断」の診断結果の項目にもなっている。●公明正大タイプ
正義感が人一倍強く、道徳心も高いタイプ。それだけに、ルールや道徳に外れたことに怒りを感じやすい傾向がある。自分の価値観を押し付けようとせず、相手の価値観を受け入れる姿勢が求められる。●博学多才タイプ
完璧主義ゆえ、自分にも他人にも厳しくなってしまう傾向があるライプ。特に優柔不断な人には怒りを感じやすい。すべての事に関して白黒ハッキリつけるのでなく、妥協点を探れるようになると良い。●威風堂々タイプ
自尊心が強いタイプ。それゆえに思い描いていた方向に物事が進まなかったり、周囲からネガティブな評価や扱いを受けたりすると、ストレスや怒りを感じやすい傾向がある。他人からの評価ばかりを気にしないことや、どちらが優秀かを競う必要があるかを見つめ直す時間を作りたい。●天真爛漫タイプ
自分の考えや感情を素直に表現でき、行動力もある一方、意思表示が苦手な人にはイライラしやすいタイプ。物事がスムーズに運ばないと怒りを生じやすい。時には立ち止まって、相手の意見に耳を傾けてみては。●外柔内剛タイプ
表向きは柔和だが、自分の意見や意思に固執しすぎるため、意見や価値観が合わない場合には内側に我慢やストレスを溜めやすいタイプ。やりたくないことを頼まれたときに、断り切れずにイライラを感じてしまうことが多い。キッパリ断る意思を見せるか、ストレスを溜め込まない発散方法を見つけると良い。●用心堅固タイプ
真面目な性格で警戒心が強く、自分の領域に入り込まれると、ストレスや怒りを感じやすいタイプ。頼られることが苦手。思い込みを捨てて、相手を信じて頼ってみるのも大事だ。簡単! 怒りを抑える「アンガーマネジメント」の方法
次に、研修などでも役立つ「アンガーマネジメント」の方法についても説明しよう。●6秒数える
これは、6秒ルールとも呼ばれている。怒りが込み上がるとアドレナリンが分泌されていく。そのアドレナリンは、6秒間で一気に体内を巡るとされている。言い換えれば、この6秒間を乗り切ることができれば、怒りは制御できるということだ。怒りやイライラを感じた際には、シンプルに6つ数えることを心がけてみたい。他にも、深呼吸をして心を落ち着かせる、その場を一旦離れるなどの行動もお勧めだ。●怒りに点数をつけてみる
これは、スケールテクニックと呼ばれる手法だ。怒りを感じた時に、その度合いを数値化してみると、怒りを客観視でき、鎮静化に役立つ。例えば、怒りの度合いを0から10まで11段階に設定し、今日の怒りが従来までの怒りの経験と比較して何点になるかを評価してみよう。これを繰り返すことで、次第に「これは怒る必要のないことだな」と気づけるようになっていく。●自分の許容範囲を広げる
「ここまで」は受け入れられるという、自らの許容範囲を越えると人は怒りを感じやすくなる。ただ、当然ながら、「ここまで」の範囲は人によって違う。相手の信条や考えが、それほど大きく異なっていないと思えるのであれば、多少の違いを理解し、受け入れられる範囲を広げてみると、怒ること自体が減っていくとされている。また、新しい体験を経験することも、価値観の拡大につながる。●思考をストップさせる
ストップシンキングと呼ばれる方法だ。怒りの感情が湧いた時に、その怒りにとらわれてしまうと感情はどんどん膨れ上がってしまう。そうならないためにも、すべての思考を止めることも有効だ。思考を強制的に断ち切ることで、自分を抑えられ、衝動的な行動を避けられる。●心の中で落ち着かせる言葉を唱える
これは、別名コーピングマントラと言われている。日頃から怒りの感情が湧いてきた時のために、気持ちが落ち着ける言葉を用意しておき、いざという場面でその言葉を心の中で唱えるというものだ。冷静に対処できるようになるだろう。また怒りが湧いた時こそ、落ち着いた口調で話すのも効果的だ。●全く異なるものに意識を向けてみる
これは、グラウンディングと呼ばれる手法だ。怒りの感情が生じたことに気づいた時に、全く異なるものに注目し、意識をそらしてみる。思考や視点を変えることで、怒りの感情から距離を置くことができるとされている。社内の「アンガーマネジメント」研修のポイント
●対象は管理職だけでなく新入社員も含める
アンガーマネジメントのスキルは、部下をマネジメントする管理職だけでなく、入社したての社員にとっても有用だ。新入社員は不慣れな環境や初めての業務で少なからずストレスを抱えている。その影響で生まれた怒りをうまくコントロールする必要がある。●内容を社内で共有する
全社員に向けて研修を実施するか、あるいは、限定的だった場合は実施後に研修内容を社内で共有することは非常に重要だ。アンガーマネジメントに対する理解を全社員で深めることによって、日常の会話で相手を思いやる空気が醸成されやすくなる。●復習の機会を作る
知識というのは一度理解したつもりでも、時間が経つと忘れてしまうものだ。アンガーマネジメントの知識やノウハウを定着させるためにも、繰り返し復習する機会を社内で作るのが望ましい。まとめ
「アンガーマネジメント」では、すべての怒りを悪とする、怒りそのものがいけないというわけではない。時には、怒りが何らかの行動を起こす重要なエネルギーになり得るからだ。問題なのは、不必要な怒りである。これは、結果的に自分自身を苦しめるだけではなく、周囲との人間関係をも壊してしまう可能性がある。「アンガーマネジメント」を身につけ、誰もが怒りの感情と上手く向き合えるようになると、コミュニケーションがスムーズになり、職場環境の改善も進むはずだ。お互いにストレスが溜まらない働き方ができるようになるに違いない。- 1