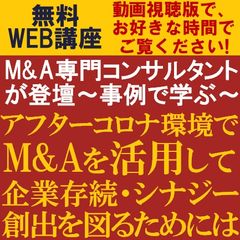◆心当たりありすぎ?!こんな社員にどう対応する?
たとえば、あなたの会社でも、以下のような社員に頭を抱えていませんか?【メンタル脆弱型】
・打たれ弱く、注意をしたり、叱ったりすると激しく落ち込む。
・教科書のない業務を与えたり、業務量が増えたりすると精神的につぶれる。
【自己中心型】
・自己愛や自己肯定感が強く、上司や取引先に対しても先輩風を吹かし、平気で失礼な態度をとる。
・自分が正しいと信じ、上司の指導や助言に耳を傾けない。
・機嫌の良し悪しをあからさまに表にだす。
【クレーマー型】
・権利意識が強く、仕事は危なっかしいのにクレームは立派で、業務について指摘しても不満を示したり、言い返したりする。
・勉強熱心で、労働者の権利についてはネット等で多数の知識を得ているが、同程度の意欲や能力を業務に対して発揮しない。
・職場や他人に対する自己の不満、悪口等を過大に吹聴したり、SNS等にアップして拡散したりする。
【コミュニケーション支障型】
・悪意はないが、発言や行動が常にずれており、周囲とかみ合わない。
【ゆとり型・怠業型】
・トイレ休憩が多い・長い、自販機の前や屋上等の業務に無関係な場所でしばしば目撃される、自席で頻繁にスマホ操作等の短時間の内職を繰り返す。
・悪天候の日や、注目されるスポーツの試合が夜間に中継された日の翌日は、高確率で体調不良を理由とする有休を取得する。
・緊急性・重大性の高い突発的な業務より、期待値低めの合コンを当然に優先する。
では、このような問題社員に対して、企業はどのような心構えでいればよいのでしょうか。ポイントは「長期的かつ前向き」に考えることです。
社外に出すときは心配、社内にいるときは周囲が困惑…そんな問題社員に対しては、企業側としては、「できることなら辞めてほしい」というのが本音かもしれません。
しかし、日本において解雇が認められるための法的ハードルがきわめて高いことは、周知のとおりです。解雇処分を裁判で争われた場合、裁判所にその有効性を認めてもらうためには、高度な合理的理由と相当性が求められます。
また、社員との合意による退職という形をとる場合も注意が必要です。後日、退職を強要されたなどと主張され、紛争になる場合もあります。
ですから、問題社員がいる場合、企業の心構えとしては、「この社員とこれからも長く付き合っていくんだ」という意識を前提に、まず、「どうしたらこの社員を改善できるか?どうしたらこの社員の能力を発揮させることができるか?」という前向きな模索をすべきです。
具体的には、適切な人物からの注意指導、担当業務の変更、配置転換等が考えられます。
問題社員の中には、たとえば、社内・社外問わず人と緊密に連絡をとりあったり、関係者間で調整したりしながら進めるような業務は不向きでも、単独で完結できる事務作業には高い能力を発揮する、という方もいます。また、人間には相性の良し悪しがあります。配置転換をして、一緒に業務を行う上司や同僚が変わったことで、周囲との波風が生じにくくなったというケースもあります。人事的な措置に先立ち、本人と個室でゆっくり面談する機会を設け、本人の認識や希望を共有することも有効です。
これらの試みを繰り返し行うことが必要となるケースも多いです。焦ることなく、長期的な目線をもちましょう。
◆業務命令違反、その時に大事なことは?
一方で、就業規則違反・業務命令違反に該当する行為については、明確にその旨を指摘し、事案に応じて適切な処分を行うなど、毅然とした対応をとる必要があります。たとえば、自席でプライベートのスマホを操作する、私語や雑談に花を咲かせる、長時間離席をする、始業時刻ぎりぎりに出社して出社記録をつけた後、食事、トイレ、一服等を行う…これらの行為は、多くの企業が就業規則で定めている「職務専念義務」に違反する行為となりえます。
このように勤務態度に問題のある社員や、業務の成果に問題のある社員に対しては、明確に具体的な業務を指示することが有効です。明確に具体的な業務を指示したにもかかわらず、身勝手な理屈で業務を怠ったり、指示に従わなかったりした場合は、業務命令違反となります。また、指示する業務が定量的な業務であれば、本来ならどの程度の能力が求められていて、当該社員はどの程度能力が不足しているのかという点が、客観的にもわかりやすくなります。
就業規則違反・業務命令違反となる行為に対しては、その内容に応じて、適切な処分や賞与査定・昇給査定等における考慮を行い、当該社員に問題点の認識・理解を促しましょう。
処分の具体的な内容としては、軽微な違反であれば、口頭注意から始めて、なお改善されない場合は、書面による注意、戒告、けん責…と処分を重くしていくことになります。
書面による注意の中でも、その作成名義を直属の上司とするのか、人事部長とするのか、担当役員とするのか等によって、段階を設けることができます。
また、企業に必ず取り組んでいただきたいのは、記録に残すことです。
記録には、どのような問題行為があったかという点のみならず、それにより業務や同僚にどのような支障・影響が生じたのか、問題行為に対してどのような指導・処分をしたのか、その後問題点がどの程度改善したのかもあわせて記録します。
記録する際は、客観的な事実である5W1Hを記載するように努め、記録作成者の評価等の主観を含めないようにしましょう。また、関係する客観的な資料があれば、それもあわせて保存しましょう。外部の第三者(紛争になった場合は裁判所)が見たときに、何があったのかが一見してわかる記録となるように意識して作成することがポイントです。
このような積み重ねを丁寧に行うことによって、最終的に解雇に至った場合はもちろん、それ以前の懲戒処分を行った場合においても、当該処分の有効性が裁判で争われた際に、企業の主張がぐんと認められやすくなります。
どうしても対処のしようがない、「問題社員」と言わざるをえない社員がいる場合には、将来的な解雇も念頭においたうえで、対応を重ねていくことも考えられます。解雇の有効性に不安のある場合は、紛争予防のために、事前に弁護士等の専門家に相談することも一案です。
角谷 美緒(かくたに みお)
奧野総合法律事務所・外国法共同事業 アソシエイト弁護士
事業再生・倒産、各種契約書の作成、コンプライアンス対応等の企業法務、一般民事・家事事件等に従事。